
 高千穂シラス(本社・宮崎県都城市)が「シラス」を使った100%自然素材の内装用左官材として「薩摩中霧島壁」を世に送り出して15年。田畑に向かず、豪雨のときには土砂崩れを起こすとして「南九州の厄介者」とされてきたシラスに注目して製品化、オンリーワンのやり方で広めてきた。そんな高千穂シラスの新留昌泰社長と、シラス壁の製品化に協力、発売後も壁材の定番として使い続けてきた建築家・伊礼智さんに対談いただいた(聞き手:新建新聞社代表・新建ハウジング発行人・三浦祐成)
高千穂シラス(本社・宮崎県都城市)が「シラス」を使った100%自然素材の内装用左官材として「薩摩中霧島壁」を世に送り出して15年。田畑に向かず、豪雨のときには土砂崩れを起こすとして「南九州の厄介者」とされてきたシラスに注目して製品化、オンリーワンのやり方で広めてきた。そんな高千穂シラスの新留昌泰社長と、シラス壁の製品化に協力、発売後も壁材の定番として使い続けてきた建築家・伊礼智さんに対談いただいた(聞き手:新建新聞社代表・新建ハウジング発行人・三浦祐成)
―「薩摩中霧島壁」が15年。その間、住宅業界も健康、自然素材、エコなどをキーワードに本質回帰が進み、良い設計を評価する目・市場が住み手・工務店双方に培われたように見えます。「つくって売って壊してつくる」から、「いい家を大事につくって長く大切に使おう」という流れに変わってきたのではないか。その中でシラス壁材も本質を評価する人に支えられてきたように思います。
新留 私は工務店等の事業を手がけてきましたが、他社と競争するのではなく、常に独自の商品、独自のビジネスモデルをつくることに集中してきました。シラス壁材でも、だれも注目していなかったシラスで建材をつくり、だれもやっていなかった工務店直販と左官職人の組織化を進め、シラス壁材だけで今や10億円の市場を築くことができた。
推奨左官店制度では、これまでに全国300以上の左官屋さんに、シラス壁の基礎知識から塗り方までを徹底的にガイダンスし、シラス壁材への理解を深めてもらいました。
―そもそもなぜ壁材をつくろうと思われたのか?
 新留 私はもともと設計事務所をやっていましたが、マネジメントが自分の強みだと気がついて昭和49年に工務店を始めました。
新留 私はもともと設計事務所をやっていましたが、マネジメントが自分の強みだと気がついて昭和49年に工務店を始めました。
両方を経験したことで、私のなかには工務店と建築家が協働しなければいい家はつくれないという明確なイメージが生まれました。その際、『建築家とつくる家』のビジネスモデルを考案し、伊礼さんともたくさん仕事をしましたね。伊礼さんのように力のある建築家のデザイン・設計の力と素材の力をトータルで融合すれば、必ずいい家がつくれるはずだということです。
では素材はどうするか。漆喰は高すぎた。珪藻土も使いましたが、当時は建材として未完成だった。だったら本物の壁を自分でつくろうと。そのとき故郷のシラスが原料として頭に浮かんだのです。
―シラスは宮崎の人に身近な存在だった?
 新留 第二次世界大戦のとき、シラスの洞窟が無数につくられました。食糧のもちがよくなるという理由で、食品庫として使われていた。子どもの頃はこの廃坑でよく遊んだものです。なぜか落ち着くし、ひんやりして気持ちがいい。空気の質が違う。私はシラスが悪いものであるはずがないと思った。しかも、山という山がみんなシラスで、資源は無限ですから(笑)。
新留 第二次世界大戦のとき、シラスの洞窟が無数につくられました。食糧のもちがよくなるという理由で、食品庫として使われていた。子どもの頃はこの廃坑でよく遊んだものです。なぜか落ち着くし、ひんやりして気持ちがいい。空気の質が違う。私はシラスが悪いものであるはずがないと思った。しかも、山という山がみんなシラスで、資源は無限ですから(笑)。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。







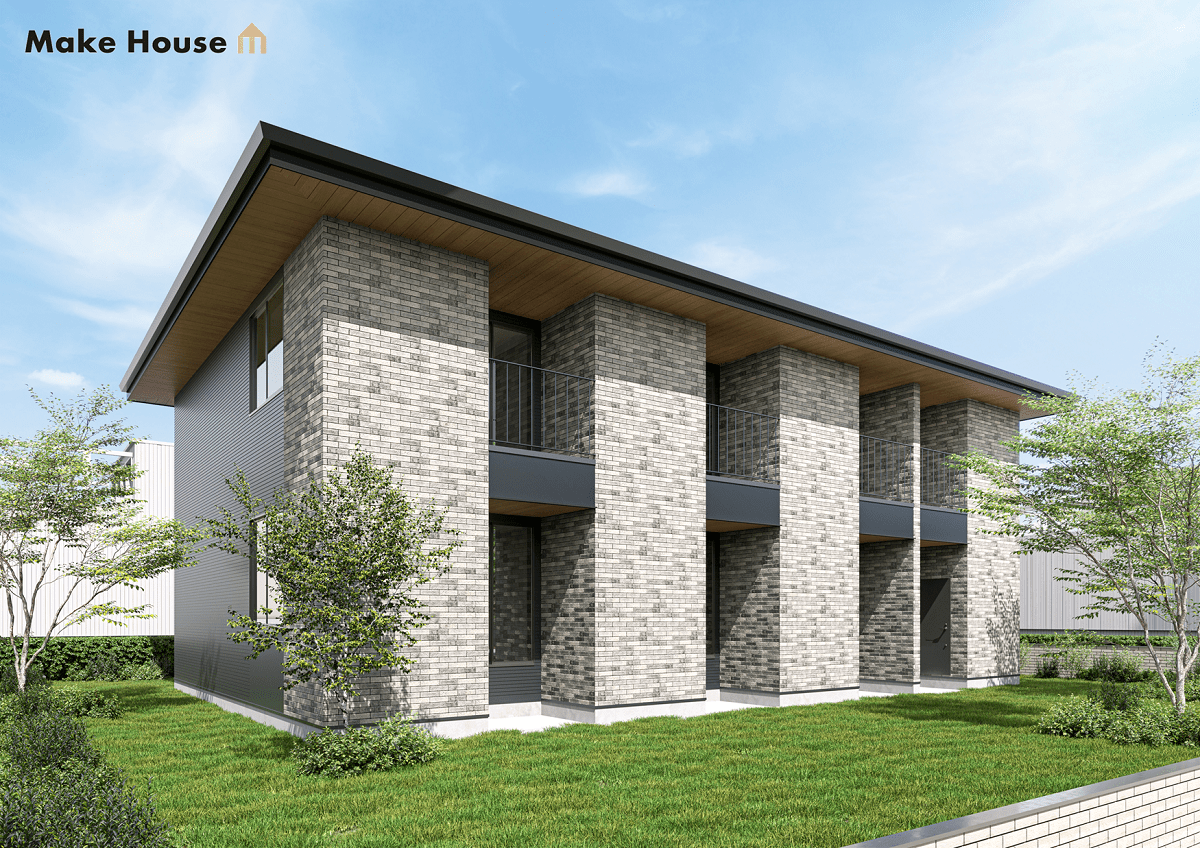

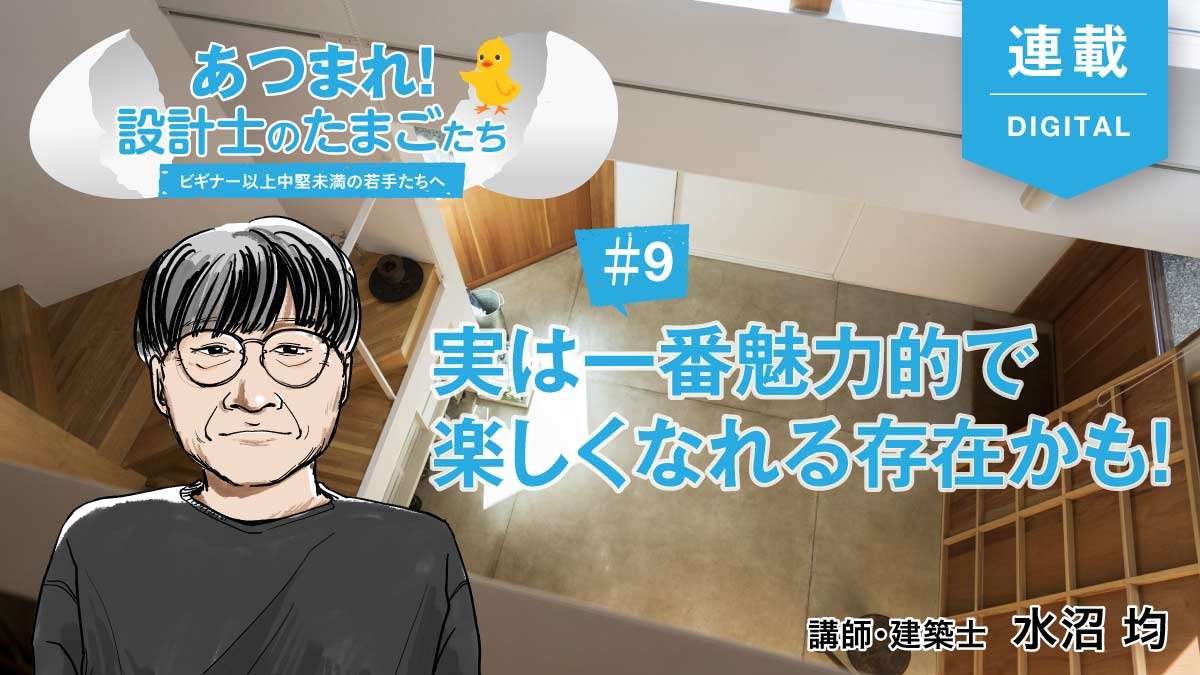



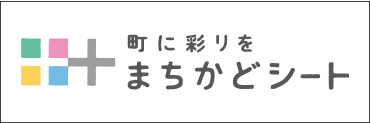













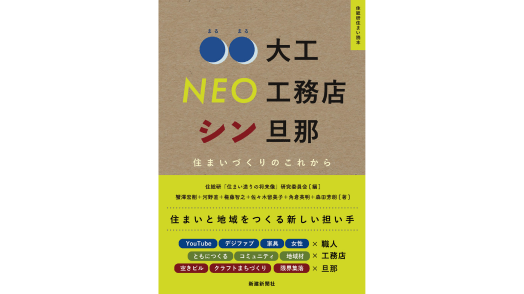


![[改訂版]コンクリート構造物の電気防食Q&A](https://www.s-housing.jp/wp-content/uploads/2023/09/db442e89b62f5b22d830d9615e68f2aa.png)
