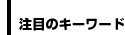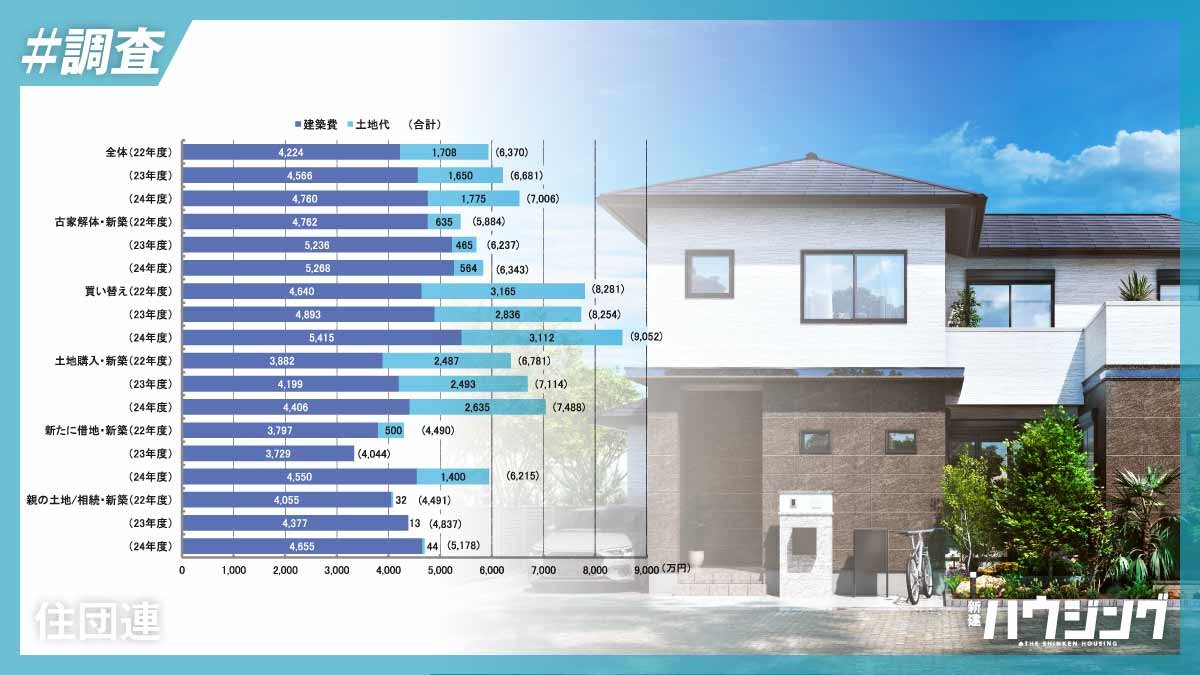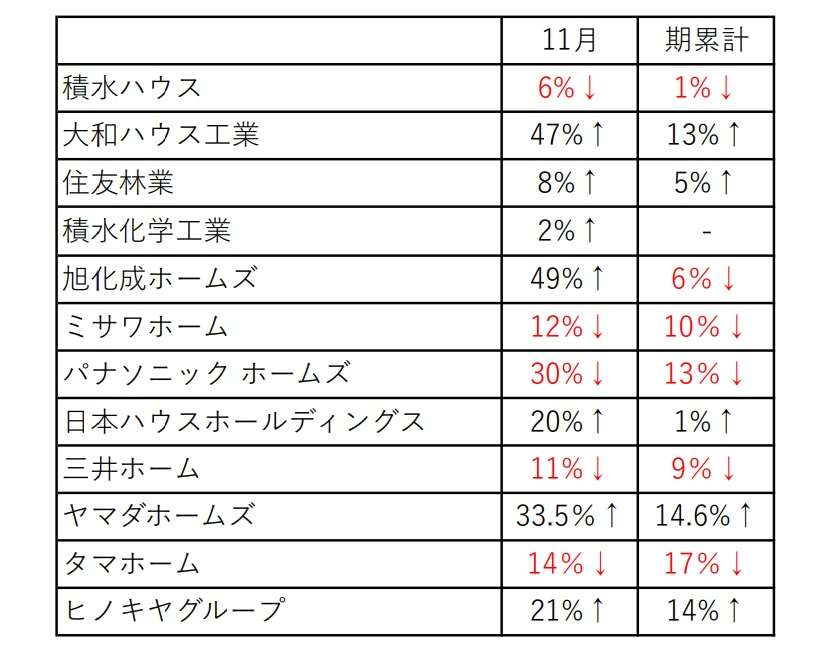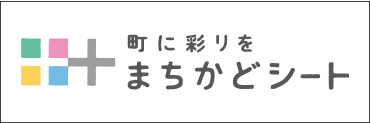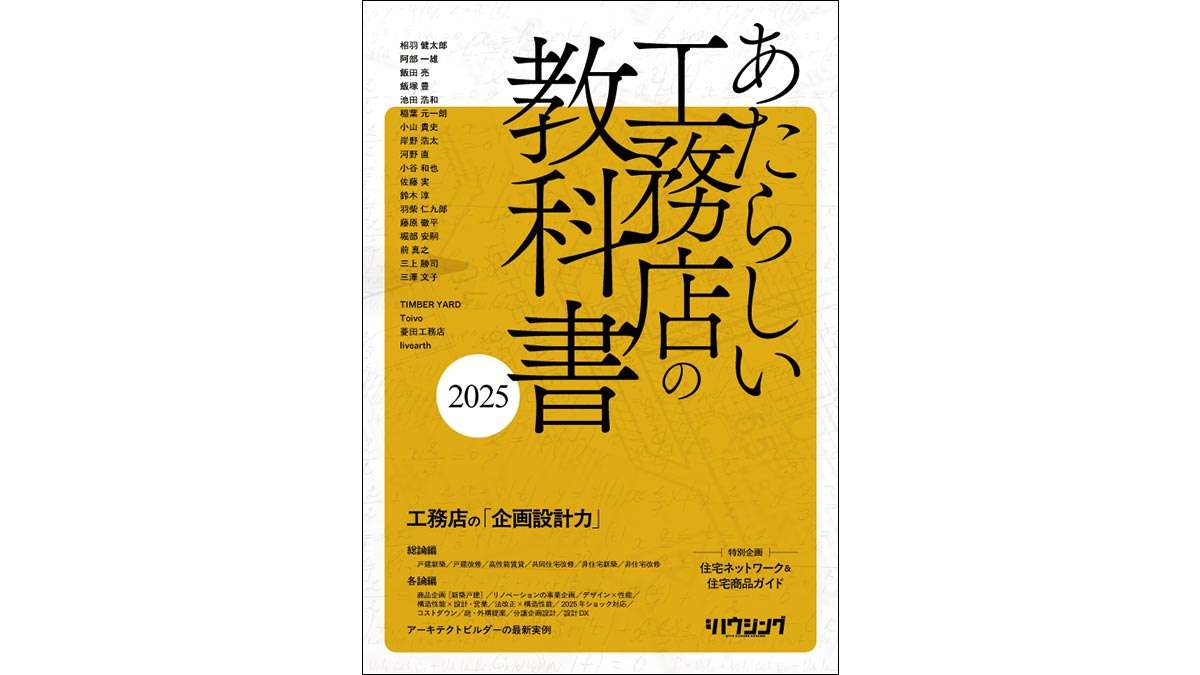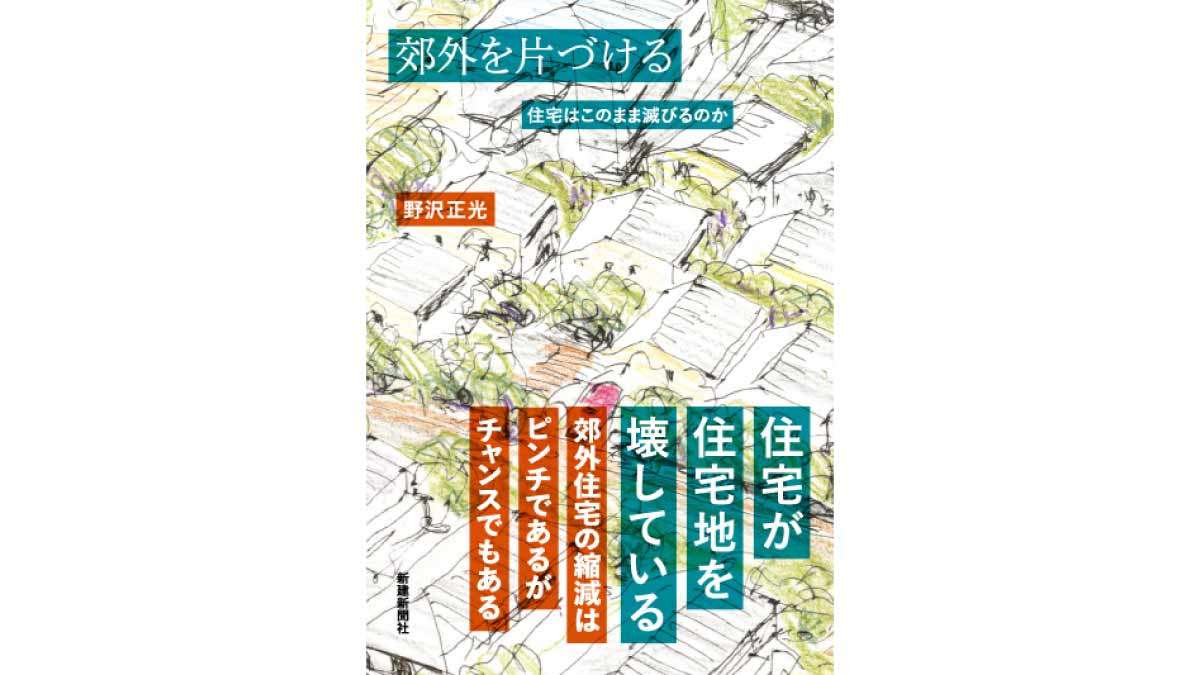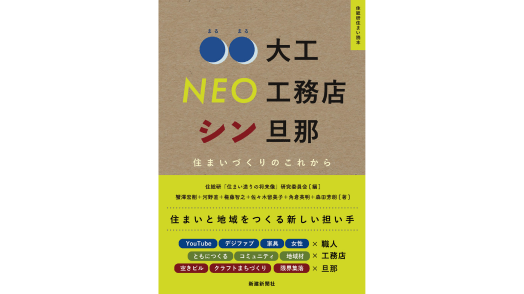山崎 亮氏インタビュー
「地縁型」とは別のコミュニティーへ
関係の切れた社会は「つまらない」
「個人の自由」が前提となった社会で、人の「つながり」が希薄化。都市部ほどその傾向は強く、自治会加入率が4割を切る地域も珍しくない。同じ地域に住む人同士が力を合わせて生活を守る、生活の質を高めるという概念はいつしか共有されなくなった。2月に東京を襲った大雪では、雪かきをしている場所としていない場所の差が歴然だった。コンビニやチェーン店でアルバイトしている若者にとって、雪かきは行政がやってくれる感覚だろう。雪かきという生活習慣自体が断ち切れている。
コミュニティーという新世界
だが、人口減と少子高齢化のなかで、まちのことは行政にお任せとはいっていられない。まちのマネジメントには住民参加が不可欠。昔であればあたり前の行動だ。住民はこれまでずっと、さまざまな共同作業を通じて相互に理解し合い、情報を交換し、経済的豊かさとは別のところで安心の生活基盤をつくり出してきた。
その実感は、確かに薄れている。が、いま「つながり」に関心を持つ若い人が増えてきたのは興味深い。ただし「昔はよかった」というノスタルジックな憧れとは無縁の感覚。彼らは昔ながらのコミュニティーをイメージしているのではなく、関係性の切れたいまの社会を「つまらない」と感じている。世代の「直観」というほかない。
前の世代には、逃れてきた記憶がある。つながりの強さは、個人の自由という観点からは窮屈だ。集落でのしきたりやしがらみは煩わしく面倒くさい。そこで育った世代が親から「都会に出て大学に行き役所か大企業に入れ」といわれ、実際にそうして自立し、故郷には戻らない、と。
そうした人たちには、互いに干渉せず隣に誰が住んでいるかもわからない都会の生活はむしろ清々と映ったかもしれない。が、彼らの娘・息子は最初から近所と付き合わない生活が普通。小さい頃は学校の友だちとつながりながら生きているが、大学に行って一人暮らしをすると本当に一人。しがらみから逃れてきた一人ではなく、最初から一人だ。
そうした若者が「みんなと食べたほうがおいしい」「みんなと見たほうが面白い」と、直観的に思いはじめた。大勢で何かをいっしょにやり感想をいい合うことで喜びが倍増する。そうした感覚を共有するいまの世代にとって、コミュニティーは新しい世界だ。
「地縁型」と「テーマ型」の融合
厳密ないい方をすれば「アソシエーション」(=共通の関心や目的を持つ人々の集団)が正しいかもしれない。それを彼らはコミュニティーとひとくくりに呼んでいる。それは悪いことではない。
世代の直感が求める新しい人の輪
「コミュニティー」には「地域共同体」の意味合いがある。一定の世代から上の人には懐かしさ(また煩わしさ)を伴うものだろう。が、若い人はそれを知らない。自治会費を払った経験もない世代が「コミュニティー」という人の輪を求めている。私はこれを「テーマ型コミュニティー」と呼び「地縁型コミュニティー」と分けている。
「地縁型コミュニティー」の代表格は自治会だ。そのため「地縁型コミュニティー」の再生とは、下がる一方の自治会加入率を上げることに等しい。悪くはないが、自治会費を払って「地縁型コミュニティー」に入るメリットを感じない若い人が多いのが現実だ。
主な活動といえばゴミ当番と回覧版、一斉掃除。秋祭り・夏祭りなどイベントもあるが、内容は前例踏襲で高齢の3役が決めてしまう。ならば「会費を払ってまで入らなくていい」と。そういう人が増えるのは致し方ない。
だが「テーマ型コミュニティー」――NPOやサークル、クラブ活動、サイバー空間上のつながりであれば、若い人が入りやすい。 そこで、そうしたコミュニティーがまちにどう関われるかを考え、何をいっしょにやれるのかを模索する。 「地縁型」と「テーマ型」がそれぞれ独自に活動しつつ、必要なときには相互に補完し合いながらまちをよくし、生活を楽しくしていく。そうした方向を考えるのが良策だと思う。(談)

|
Profile 山崎 亮氏(やまざき・りょう) studio-L 代表 1973年愛知県生まれ。大阪府立大学大学院および東京大学大学院修了。建築・ランドスケープ設計事務所を経て2005年にstudio-L設立。地域の課題を地域の人たちが解決し、一人ひとりが豊かに生きるためのコミュニティーデザインを実践。まちづくりのワークショップ、住民参加型の総合計画づくりなど80以上のプロジェクトに取り組む。京都造形芸術大学教授、慶應義塾大学特別招聘教授。 |
山崎亮氏が新建ハウジングが主催するフォーラムで講演していただきます。定員制になっておりますので、お早めにお申し込みください。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。