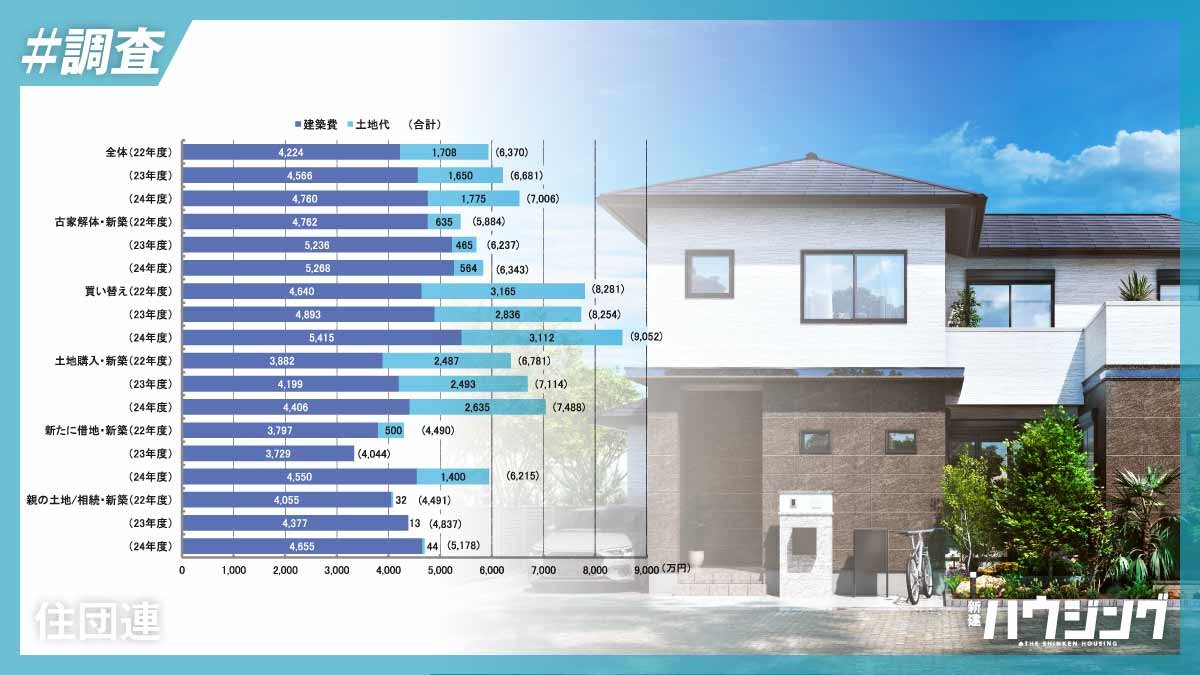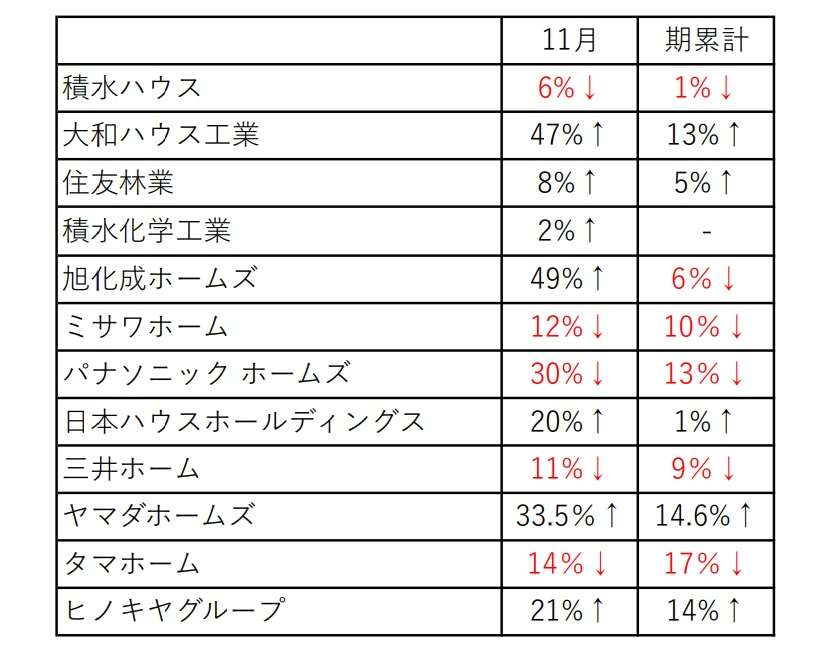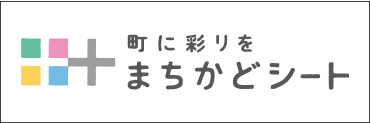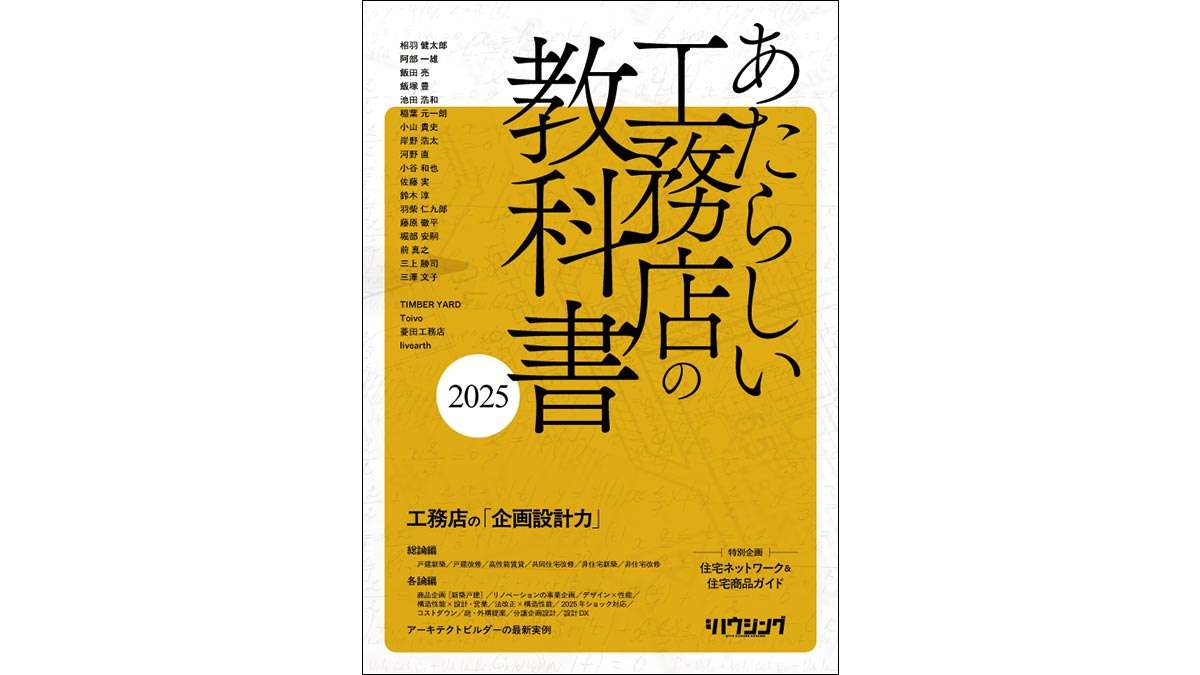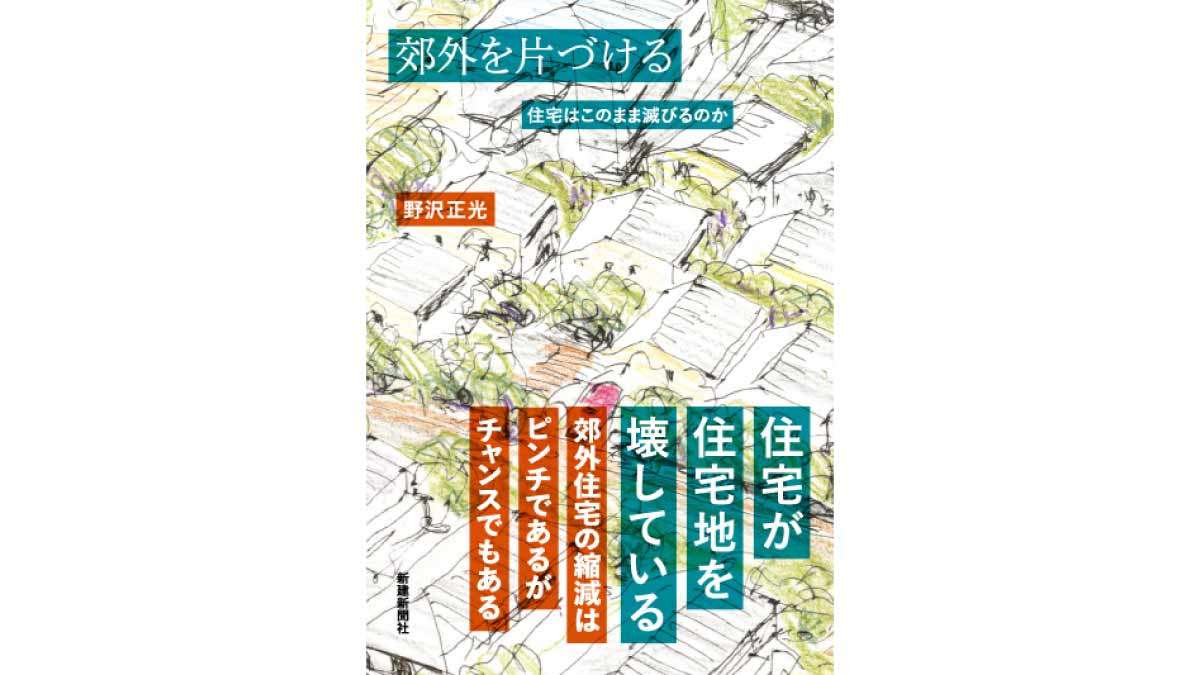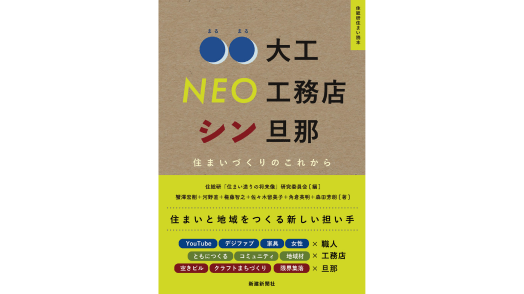吉村順三氏の木造モダニズムを受け継ぐ建築家として知られた永田昌民(ながた・まさひと)さんが12月14日(土)、72歳で亡くなられました。追悼の意をこめて、生前懇意であった小池一三氏から特別寄稿を頂きました。編集部一同、永田様のご冥福をお祈りいたします。
✳︎文中写真は永田昌民氏が2009年に設計された小池氏の娘さんご家族の自邸。写真撮影/岩為氏

*******************
嘆きの永田昌民
建築家の永田昌民さんが、12月14日早暁に亡くなった。寒い朝だった。その前年の12月に奥村昭雄さんが亡くなっていて、こころの拠りどころを失って間もないところに、永田さんの死である。
自由律俳句の尾崎放哉に「咳をしても一人」という句がある。「残された」という思いがつよい。永田さんは、ここ最近の住宅の造りようを嘆いていた。むかしは酒が入るとそういうふうだったが、ここ3年余りは電話を掛けると嘆き、会うと国の施策を槍玉に挙げたりして、慷慨を鳴らした。
そんなに言いたいことがあるならと、国交省の検討委員会の委員に推したけれど、1回参加しただけで何も語らなかった。言っても届かない連中と思ったのだろう。議論好きではあるけれど、人見知りし、気持ちの通じない人とは話さない。いうなら永田さんの悲憤慷慨は職人談議なのであって、設計の野丁場のものである。それだけに率直で真実を突いていた。
ここ数年の永田さんは怒りん坊だった。永田さんのオープンハウスには、若い人がたくさん寄ったが、全体を見ないで、建築細部の写真をパシャパシャと撮り、巻尺で寸法をあたる無遠慮を怒った。最近は、TTPとか言って、徹底的にパクルことを良しとする風潮があるが、デザインの本質に目を向けないで、表皮をなぞられるヤカラを嫌った。
建築家は、ほとんどナルシストである。真似されて悪い気はしない。けれど、越えてはならない一線がある。若手の創作精神を摘んで服従させてはならない。むろん真似ることで分かることもあり、ぼくなどそこは甘いのだが、永田さんは盗んで何が悪いという厚顔を赦さなかった。分からないように盗み、よく咀嚼して、自分のものとして表現すべきことで、それは吉村順三から学んだ、永田さん自身の態度であったように思う。
世の中、恐い人が少なくなった時代に存在を示した点で、永田さんは真の意味で教育者だった。若い人への期待を、誰よりもつよく持つが故に一徹を通した。この重石を失ったことの意味を、われわれは時を経るごとに知らしめられよう。
やさしい永田昌民
嘆き怒る永田さんと、やさしくて律義な永田さんがいた。目白の事務所を訪ねると、永田さんは鼻眼鏡で図面台に向かっていた。上目づかいにこちらを見て、うんうんと頷いて、「坐んなよ」とうながした。
窓辺にメダカが飼われていた。草藻のなかを、目を見開いて泳ぐメダカが、日を浴びて時おり銀色に光った。静謐な空気が流れていた。永田さんは坐ると、しばらく黙っていて、やおら「どう?」と聞く。主語抜きの人である。「うん、まあ」というと、ピースの箱をせわしげに弄りながら、間を置いて「そんなもんだよ」と言った。いつもそんなふうだった。仕事は、いつだって苦労の連続である。何事も簡単には行かない。永田さんには、何回も難題を持ち込み、その都度ひとかたならぬ面倒をお掛けした。何もなければ「日々是好日」である。
OMソーラーの発足時、工務店勧誘のため、全国キャラバンを行った。車を繰って敦賀からフェリーに乗り小樽に着き、札幌・函館・盛岡・仙台・福島・宇都宮・前橋・水戸を回って、東京にたどり着いた。どの会場も、参加者は少なかった。当時、工務店はバブルに浮かれていて地味な技術への関心が薄かった。結局、一社の入会もなかった。深い疲労を感じての東京入りだった。東京では永田さんが待ち構えていて、黙って食事に誘ってくれた。他愛無い話に終始した。それで救われた。その頃から、永田さんの設計のすべてに空気集熱式ソーラーが導入され、それは最後の仕事まで続いた。
実に律義な人だったが、それを自分の設計に馴染ませ、デザインとして昇華させ、このソーラーシステムを代表する建築を幾つも設計した。 『ソフト・エネルギー・パス』(時事通信社)や『新しい火の創造』(ダイヤモンド社)の著者として知られるエイモリー・ロビンスが来日した折、永田さんの建物を見てもらったことがある。ロビンスは興奮覚めやらぬうちにホテルで手紙をしたため、感想を寄せられた。天から注がれる自然の力を利用しながら、それを巧緻なデザインに高めていることに深い感銘を受けた、と書かれていた。
永田さんは、ソーラーシステムを住まい手のものにするため、あの独得の文字による手製のメンテナンスブックを作り配られた。建築家の多くは鍵を引き渡したら、それで仕事は完了すると考えがちであるが、永田さんはそれを良しとしなかった。親切心というより、それが永田さんの仕事の流儀だった。
居心地のカタチ
永田昌民の仕事を決めているのは何だろうか。どの仕事の、どこを切っても永田昌民としかいいようのない世界のものであるが、ひとつとして同じ仕事はない。どの仕事もディテールは詳細を極め、労を厭わず、一本一本の線に意思を籠めてたくさんの図面を描いた。
何がそうさせたのか。永らく助手を務めた越坂部幸子さんに聞いたら、土地を読むことに腐心し、いつもそこが出発点だった、と言われた。五感を全開させて、その土地の地味を、気配を、風を、日の光を、空気を読み、四方に目を配って、近景、中景、遠景を透視し、冬には、春には、夏には、秋にはどうか、朝には、昼には、夕にはどうなのかを感じ取り、そうして建物のカタチを求めた。

そして、ここが肝要なのだが、芭蕉が言ったという「ゆきてかえる」関係認識が、設計の基本に置かれた。この言葉は、芭蕉が書いたものではなく、芭蕉の同郷の後輩、服部土芳がまとめた『三冊子』に出てくる言葉である。連歌・連句のつけ合いの心を説いた芭蕉晩年の俳論で、『野ざらし紀行』の旅のおりに語られたといわれている。
永田さんは、建物の外と内の「ゆきてかえる」関係を、設計の表現に高めた設計者だと思う。永田さんの設計にポエジーが宿るのは、このことによる。この場合、住まいの外側からよりも、内側からの視点が細やかに、柔らかく働いて、そこが永田らしさだと、ぼくは思っている。「住まいは内側から考える」という「吉村テーゼ」の生きた教科書といえる。
ぼくの娘が仙台に嫁ぎ、家を建てることになり、設計を永田さんに依頼したいと言い出した。建築予算は1800万円である。永田さんに設計を頼む要件を欠いていると思われたが、「とにかく聞いてみてよ」と言われ、駄目元で永田さんに伺ったら、「小さい家になるけどね」という言葉を添えた上で、軽く「いいよ」という返事をいただいた。
設計過程の話は、何を諦め、何を大切にするかに大半が割かれたという。娘は、永田さんのクライアントの多くがそうであるように、最初は、美しい空間をつくってもらえるという漠然とした期待があった。しかし、予算や土地の制約など、住まうことの現実に向き合うなかで、娘はいつしか、住まうとはどういうことかを、知らぬ間に教えてもらったという。それが娘の宝になっている。
住んでみて、たとえば外の木立の芽吹きが窓を通して目に入り、それが息をのむほどに美しいと思えたり、ソファーに寛ぐ主人と、キッチンに立つ自分との絶妙の距離を感じたりと、今では永田さんの設計の仕立ての良さを心行くまで愉しんでいるようだ。亡くなったことをメールで娘に伝え、生涯164の住宅をつくられたと言ったら、「私の家は164棟のうちの一棟なのね。ストラディバリウスみたい。大事にしていきます」という返信があった。
永田さんが設計した住まいは、住まい手が居心地良く住んでいて、深い愛着を持って、大切に大切に住んでいる人が多い。施主宅を訪問して、いつも感じることである。それほどに、住まい手と濃密な交情を切り結んでいるのだから、どの家族についても記憶も濃厚だと思っていたら、意外にも永田さん自身はほとんど覚えていないという。一瞬、耳を疑った。
しかし間もなく、その理由に気づいた。その時々の仕事に、まるで鶴が機を織るように打ち込むが故に、次の仕事に入ったら、今度はそれに夢中になってしまい、過去は忘却されるのである。残るのは建物であるけれど、その空間が気持ちよく、そうしてそのディテールがあまりに巧緻に満ちているものだから、人はそこに目を注ぐのである。
協働の仕事
永田さんの仕事で忘れてはならないのは、住まいづくりは協働のものだというあり方である。永田さんは、いつも予算が頭から離れず、また担当する工務店の力量も頭から離れず、むしろそのことを仕事の課題にされた。建築家はみんなそうだよ、といわれるかも知れないが、空間への思いが先に立ち、つい現場を忘れてしまうのが、建築家の常である。

永田さんの設計とて、予算オーバーすることが多い。そこからの調整に時間を掛け、それぞれにとっていい着地点へと向かう。普通、泣きをみるのは工務店である。いかに値切ったかを手柄にする建築家がいたりするが、永田さんはそんな乱暴なことはしない。
仕事は、いつの場合も制約下のものである。その制約下でいかに最善のものをつくるか、その心尽くしが納得の結果を生むのである。そこにおいて、基底にすわるのは、協働のあり方であり、住宅は、住まい手と設計者と工務店が一緒につくるものなのだ。
ある建築家から、自分の仕事をやってくれる工務店がないので、紹介してくれないかと泣きつかれたことがある。この件について、永田さんは「自業自得だよ」と辛辣だった。仕事は普段のものであり、その積み重ねでしかない。その怠りが招いた結果であってみれば、同情なんかしないよ、と顔に出ていた。
永田さんとM&N設計室を立ち上げられた益子義弘さんから「永田もぼくも職人から仕事を教わった」という話を聞いたことがある。お二人とも、大学を出てどこかの事務所に身を置いて仕事を覚える助走期間なく独立された。
実際の現場に入ったら知らないこと、分からないことが多い。根を詰めて詳細図を描いて大工に渡すと、「これじゃあ現場は納まらないよ」といって突き返される。描き直しても首をタテに振ってくれない。また描く。ニヤッと笑って、鉛筆舐め舐め「ここはこうじゃないか」と描いてくれた。職人衆との、この刺激と緊張が永田昌民を育てた。原寸図まで描いた永田さんは、そんな経験が背景にあってのことで、お二人にとって大工や現場監督が教師だった。この「私の大学」がよかったように思う。
もし大事務所の担当者なら、それ相応の対応をされたわけで、藝大の教師を務め、ひとかどの経歴を持っているとはいえ、現場をよく知らないで飛び込んだわけで、いきなり職人衆のキツイ洗礼を受けたのである。幸運な出発だったと言えるだろう。住宅設計の名人は一夜にしてならずである。永田さんは終生、腕のいい職人に尊敬心を持ち続けた人だった。それは師匠の吉村順三、兄貴分の奥村昭雄らに通底し、この一群の建築家たちに渾々と流れる精神性をかたちづくっているように思われてならない。
永田さんは、生涯164の住宅を世に送り出した。M&N設計室の設立から実質37年。住宅以外の仕事を含めると年間5件弱。仕事の密度を考えると寡作とはいえない。むしろ多作だったといっていいだろう。住宅以外の仕事で、ぼくが知っているのは浜名湖の「地球のたまご」計画と、京都岡崎の小さな中華料理店、少し特殊な仕事として、造園家田瀬理夫さんと組まれた遠野「馬付住宅」だけである。
住宅のスケールをこよなく愛し、住宅にこだわり、数多くの珠玉の住宅を遺された。あなたに心からの拍手をおくる。
有る程の菊抛げ入れよ棺の中 夏目漱石
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。