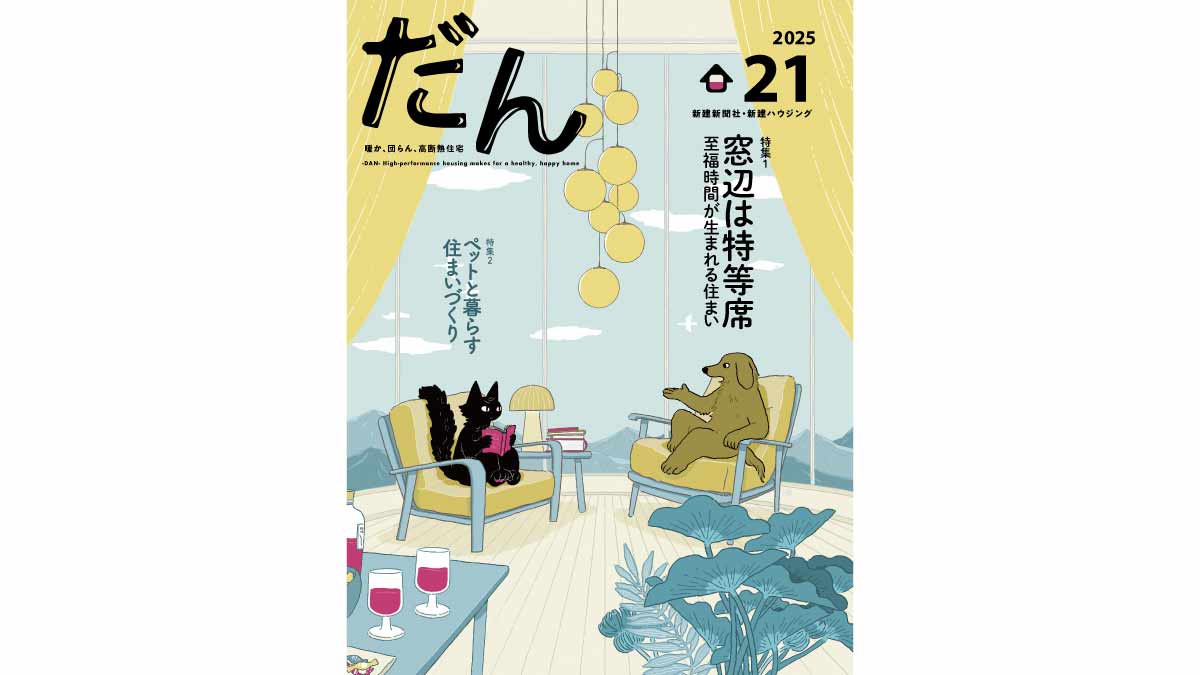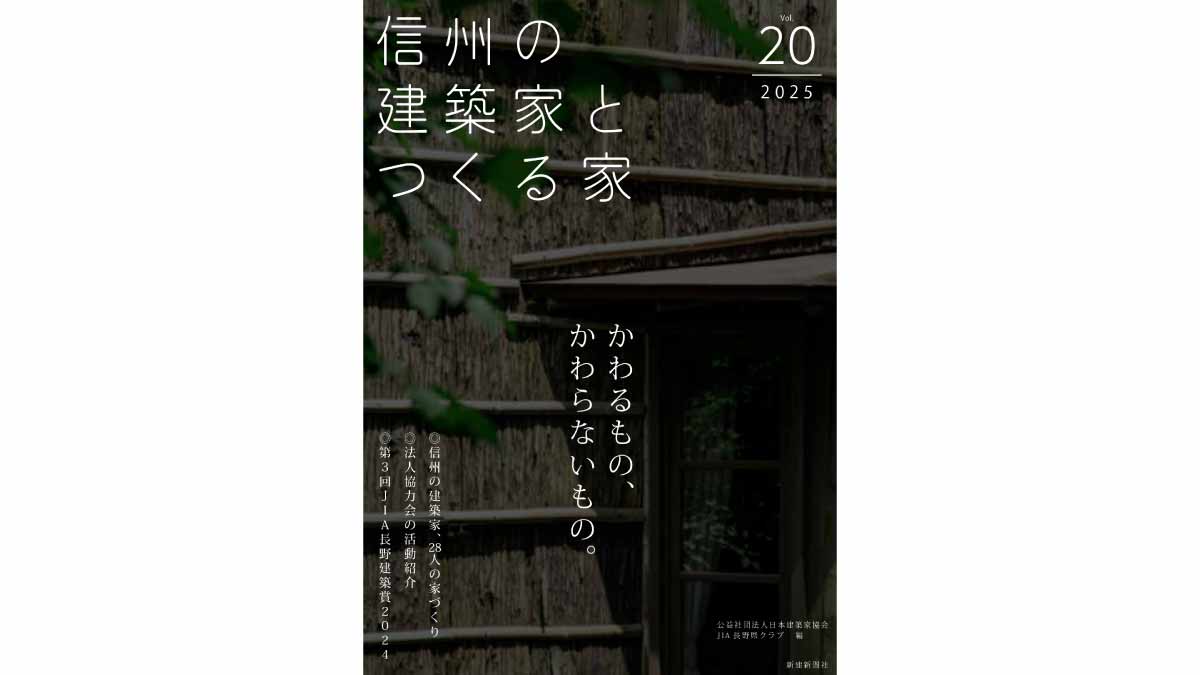国土交通省は4月1日、空き家対策に取り組む地方公共団体や事業者、団体に向けた指針として「空き地の適正管理及び利活用に関するガイドライン」を公表した。同省の土地政策研究会における議論を踏まえ、今後も増加が見込まれる空き地を適正に管理・利活用するための考え方や、具体的な取り組み事例、対策条例の内容、活用可能な制度などをまとめた。
同省が実施した土地基本調査によると、世帯の保有する空き地の面積は、2008年から2018年にかけて、632㎢から1364㎢へと2倍以上に増加。また世帯の保有する土地全体に占める空き地の割合(空き地率)も6.5%から12.4%へと増加しており、今後も増加が見込まれている。
同ガイドラインでは、空き地の発生要因として利便性の悪さによる宅地としての需要不足や、接道など建築要件の問題を挙げ、相続・贈与を契機に発生することが多いとした。そのうえで、隣地の所有者や地域の活動団体への譲渡・貸与により利用機会を付与する、利活用の用途の幅を広げるなど「可能な限り需要を見出して利活用に導く」ことが重要とした。
また、利用や管理の主体は所有者が原則だとしつつ、地域の事情に通じ、かつ土地利用の方針を定める市町村の積極的な関与が必要だとした。国は、地方公共団体のニーズに法的根拠の整備、予算措置などで対応すると位置づける。また、担い手も行政、専門家、民間事業者、NPO、団体など多岐に渡ることから、ワンストップ窓口の設置の重要性を指摘している。
その他、実際の自治体における空き地対策条例の条文や、関連法案を紹介。また、都道府県や市町村による空き地の管理・利活用に関する取り組みをまとめた事例集も作成した。
■関連記事
設計事務所が空き家をリノベし一棟貸しの宿泊施設オープン
空き家活用、先進事例を調査 自治体と不動産業者の連携後押し
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。



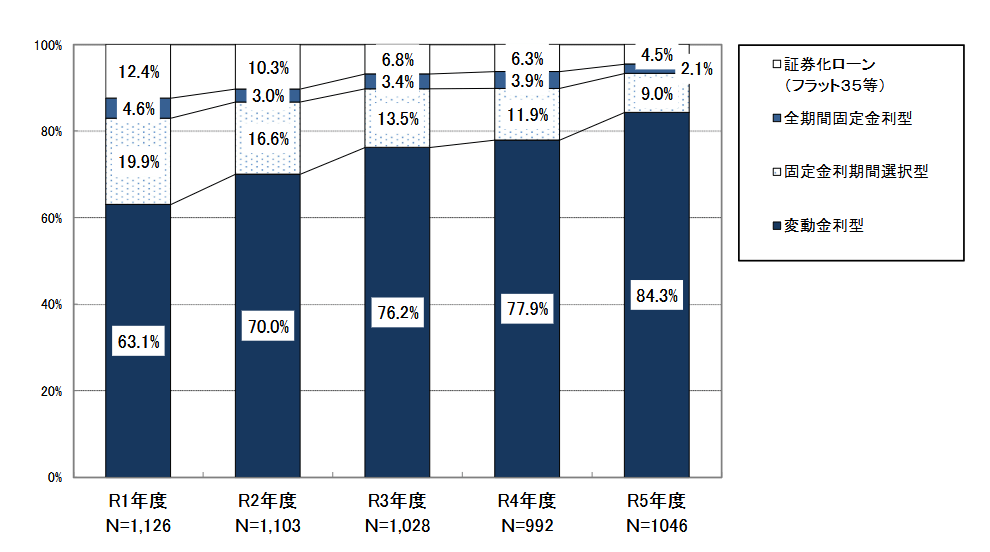
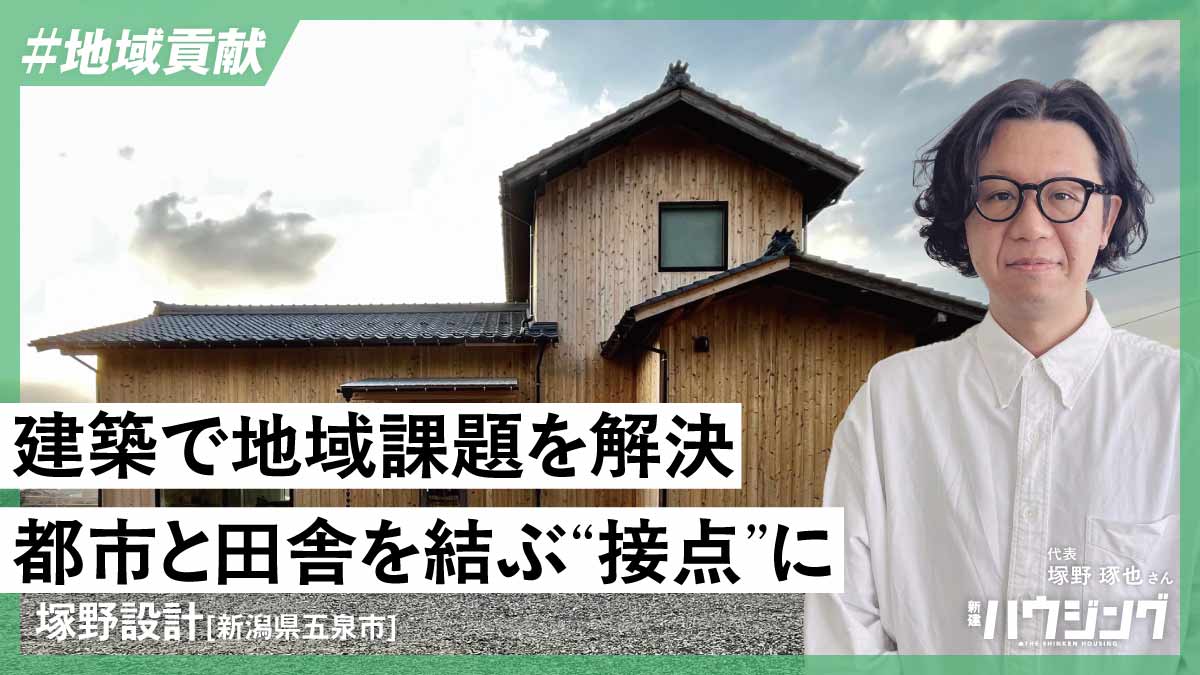



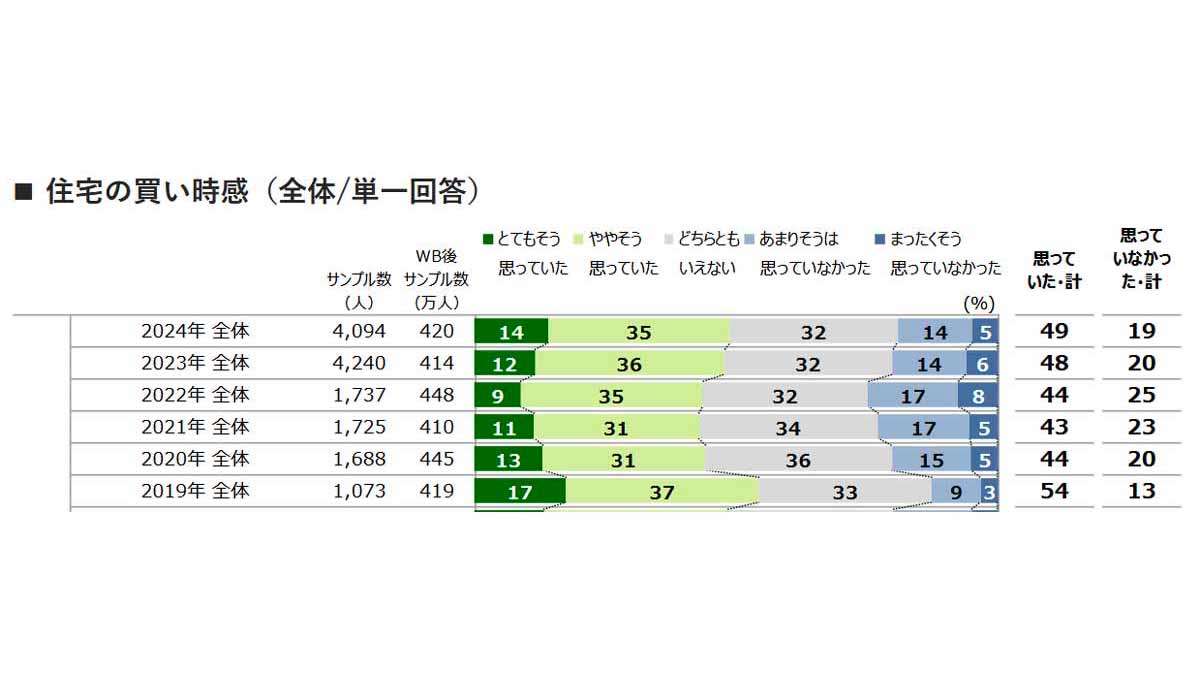
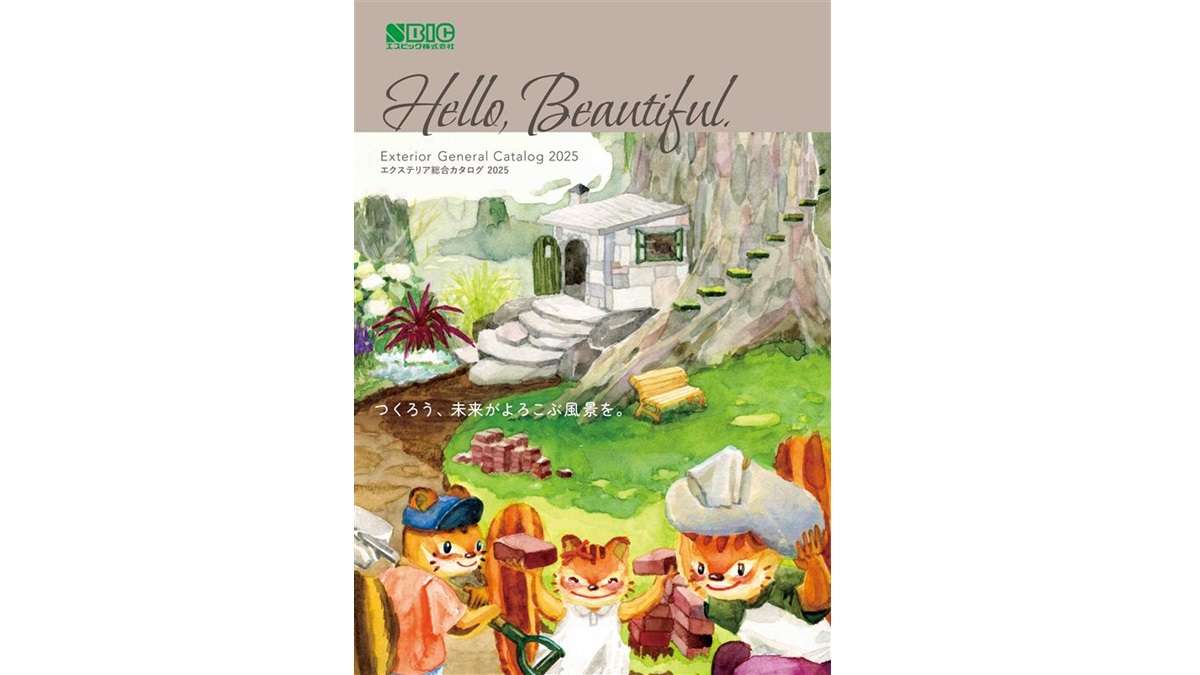



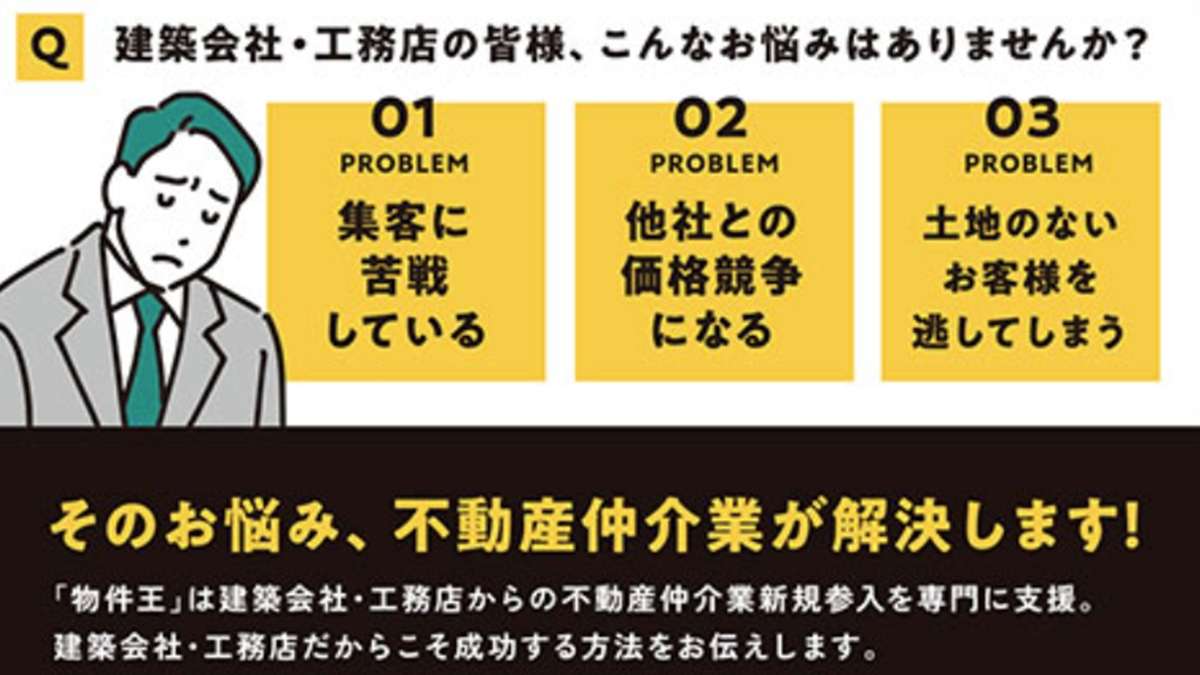











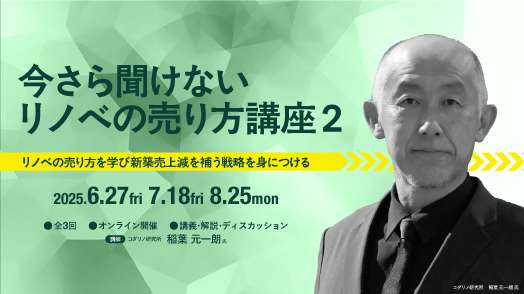
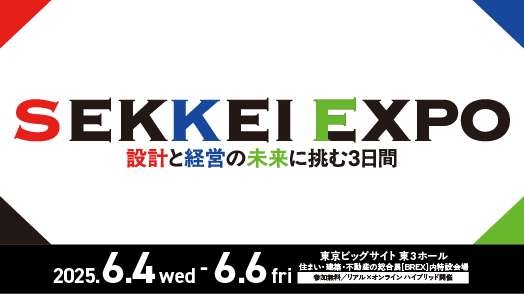



![[改訂版]コンクリート構造物の電気防食Q&A](https://www.s-housing.jp/wp-content/uploads/2023/09/db442e89b62f5b22d830d9615e68f2aa.png)