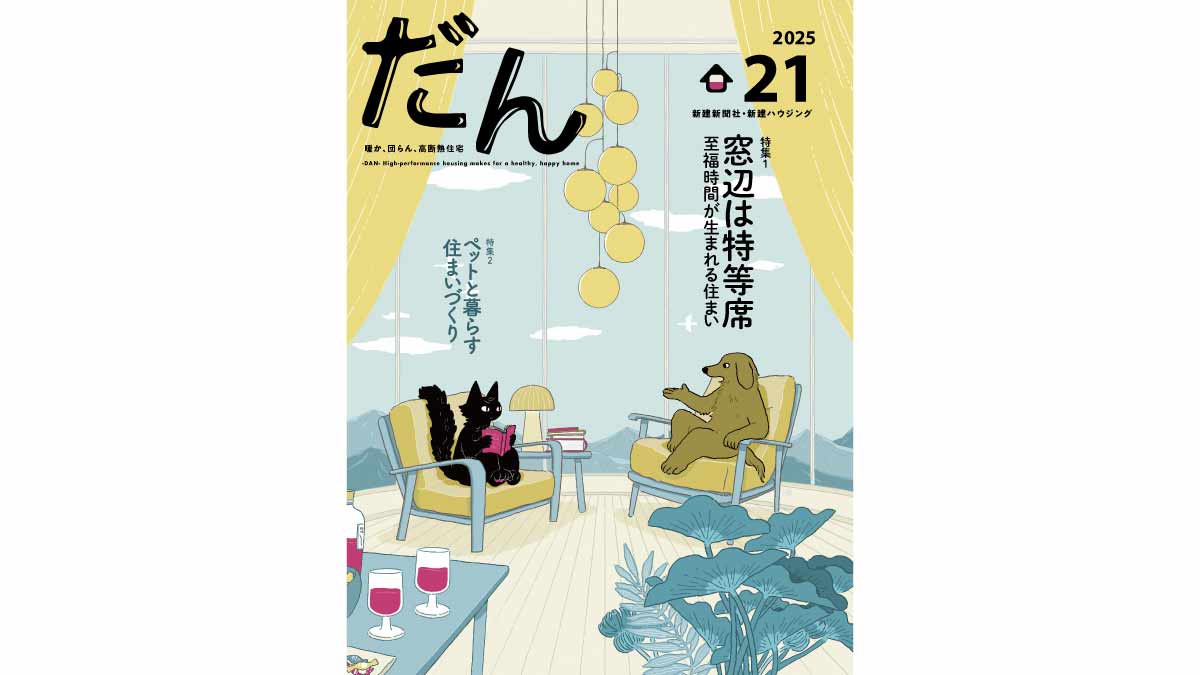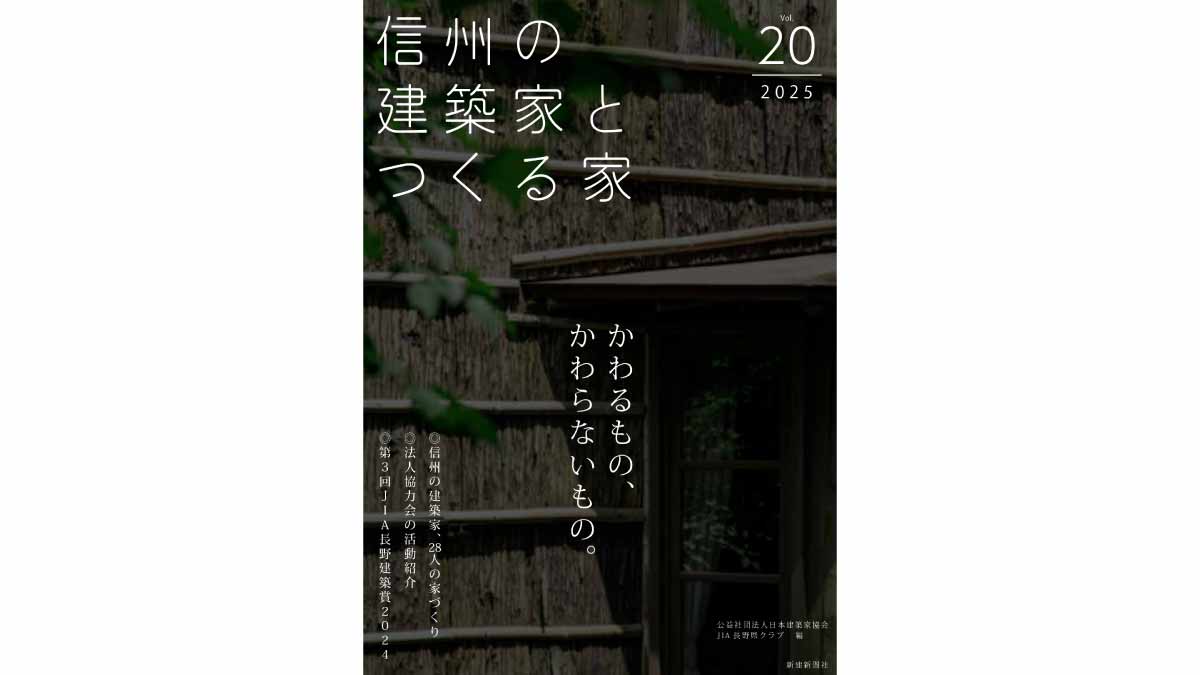「寒くない窓辺」から一歩進んだ「くつろぎの窓辺」。その勘所を東京理科大学准教授・高瀬幸造氏に聞いた。
※本記事は、新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー4月号「チルい窓」掲載の記事から、「窓配置や大きさの自由度を高める「チルい窓」をつくるための基礎知識(東京理科大学准教授・高瀬幸造氏)」の内容を抜粋したものです。
取材・文:大菅力
窓手法① 窓面積は外壁の15%程度に
● 断熱性能を部位別に見た場合、最も性能が低いのは窓。一方、眺望を優先する場合など、面積を大きくしたい部位でもある。どのように性能と居心地のよさを調整するのか
● まずは計画建物のUA値を算定。その過程で必要な窓の断熱性能を検討。たとえば寒冷地で断熱等級6以上を確保して大開口を得るには、樹脂サッシ+Low-Eトリプルガラスが必要だとわかる
● 同様に夏の熱負荷を計算。ホームズ君などのソフトを用いる。たとえば窓を大きくすると夏の日射遮蔽を徹底する必要であり、地域によっては中間期にオーバーヒートするとわかる
➡︎ 窓を大きくするには、窓の断熱性能を高めて、日射遮蔽を徹底する。その上で窓面積を外壁面積の15%程度に留める
窓手法② 方位により窓の扱い方を変える
●窓面積の影響は方位によって異なる。東・西面は冬の日射が期待できない。夏は太陽高度が低いため軒が効かず、日射の影響を受けやすい。そのため窓面積は必要最小限に留める
●北面は通年で安定した天空光を得られる。一方、直射日光は入らない。冬に日射取得は期待できないため窓辺は寒くなりやすい。窓を大きくするには断熱性能を高める必要がある
●ただし・・・
この記事は『新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー4月号(2025年3月30日発行)チルい窓』(P.33〜)をデジタル版に再編集したものです。続きは本紙でご覧いただけます。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。


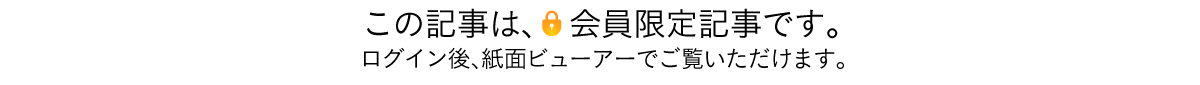


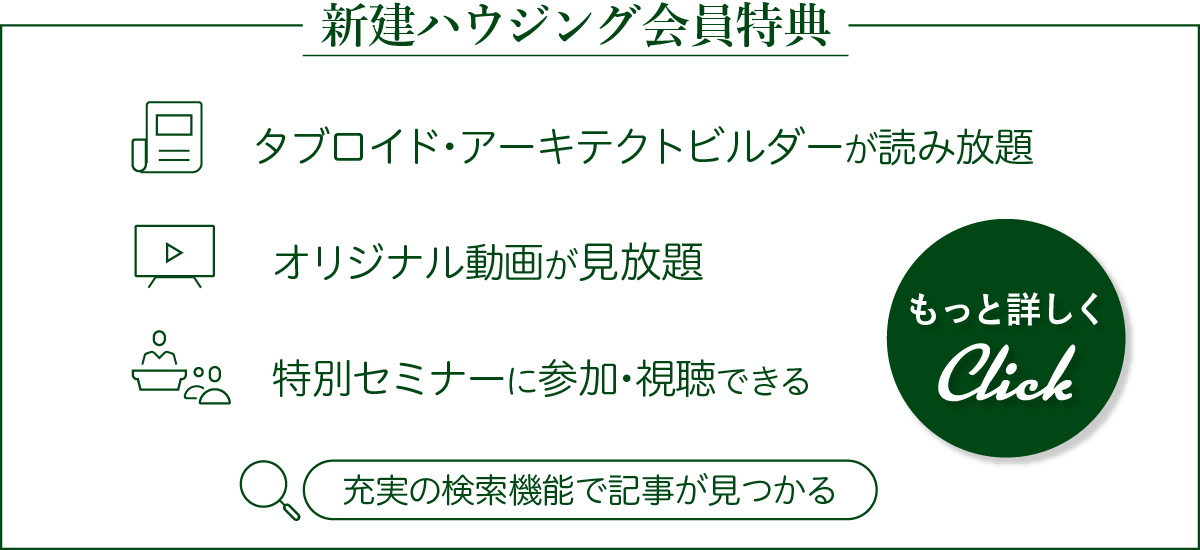














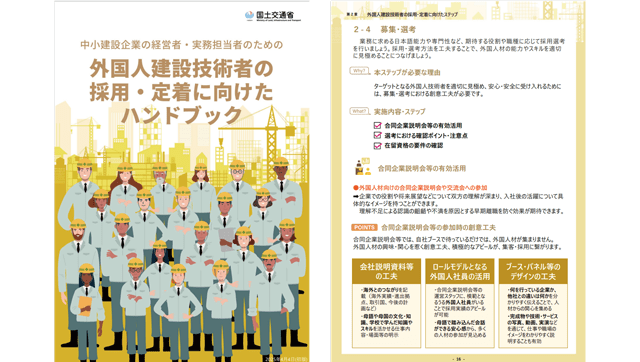









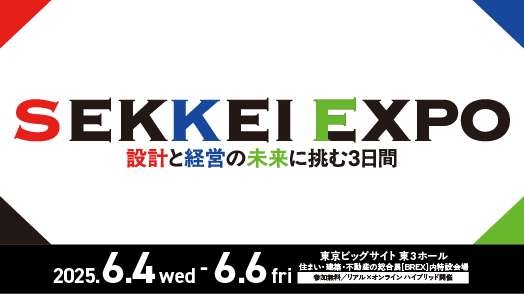

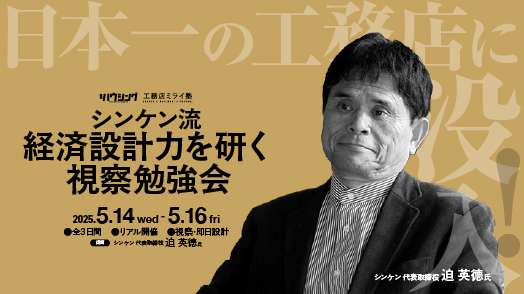


![[改訂版]コンクリート構造物の電気防食Q&A](https://www.s-housing.jp/wp-content/uploads/2023/09/db442e89b62f5b22d830d9615e68f2aa.png)