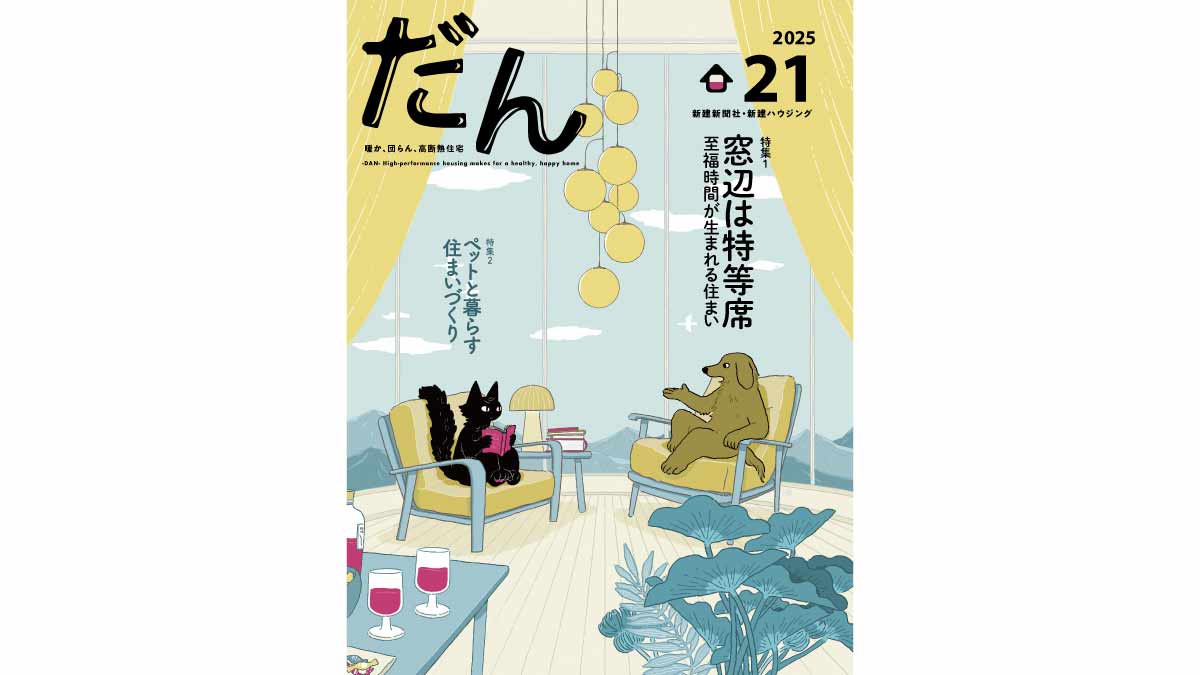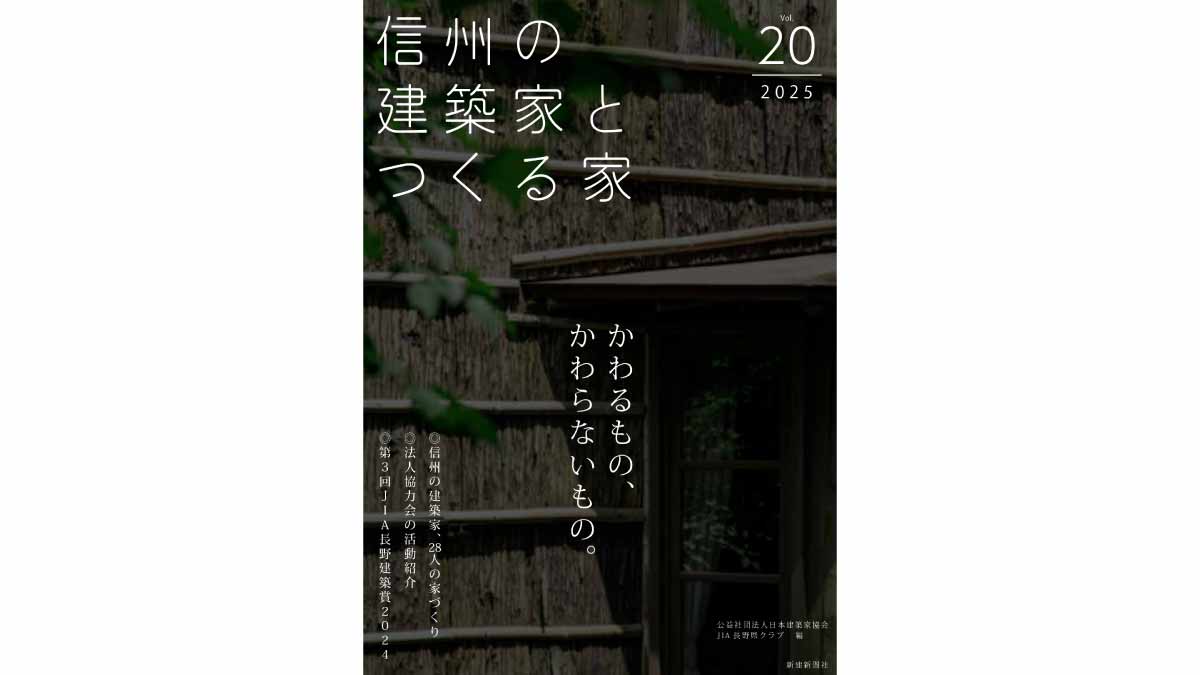今や寒くない窓辺は当たり前。差をつけるのは窓辺の居心地。「チルい=くつろげる」窓辺を実現するあの手この手を探ります。
※本記事は、新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー4月号「チルい窓」掲載の事例から、古谷野工務店(東京都板橋区)「2階リビングに多様な窓を設けて適切に内外をつなげる」の内容を抜粋したものです。
設計・施工:古谷野工務店 撮影:西川公朗、古谷野工務店
取材・文:大菅力

窓手法① 「この場所」を感じる窓の効果
● 窓の役割として「この場所にいる」ことが感じられることを重視。敷地ごと、方位ごとの外部環境の特性によって窓の開き方を検討する。基本は壁に対して窓をうがつように考える
● 窓は空間を認知させる機能も持つ。空間の隅に窓を設けて光を採り入れると、空間のかたちや広がりが伝わりやすい。同時に通風も得やすくなる
● この事例の2階LDKにおいて、積極的に外部環境を取り込んでいる窓は3箇所。外部環境や空間のなかの場所性の違いによって扱い方を変えている。窓はサーモスII-Hを用いている
窓手法② 眺望用窓は高さ寸法が大事

ダイニングから庭を見る。公園に向かって眺望用のFIX窓を設けた。幅2194㎜×高さ1300㎜。床からの高さは400㎜
● 最も外部を積極的に取り入れているのがダイニング脇のFIX窓。この場合、窓の取り付け位置は最初に床からの高さを検討。高さ400㎜に設定した。身体感覚として膝の高さが定規になる

● ソファを置くのであればその座面+α程度に考える。ソファの座面は低めだと300㎜程度からある。一般には400㎜前後が多い
● 眺望用の窓は大きく開きたい場合が多い。既製品の窓を用いる場合・・・
この記事は『新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー4月号(2025年3月30日発行)チルい窓』(P.54〜)をデジタル版に再編集したものです。続きは本紙でご覧いただけます。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。


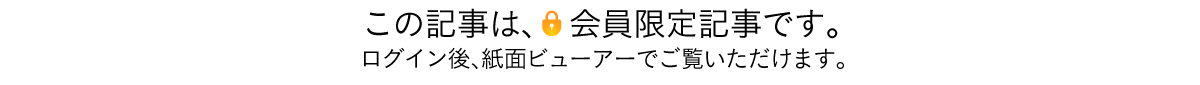


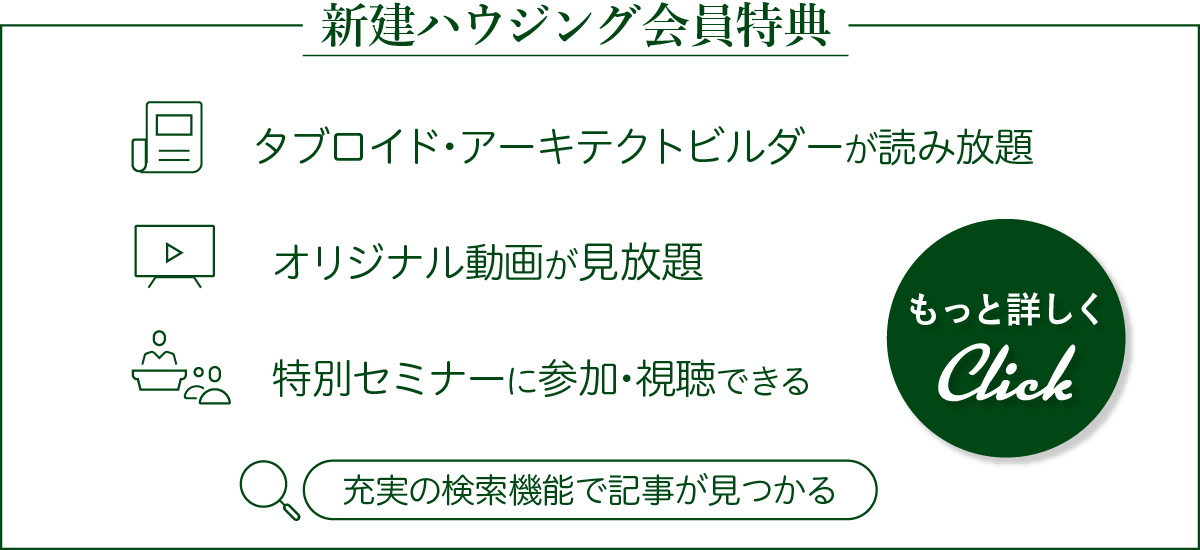







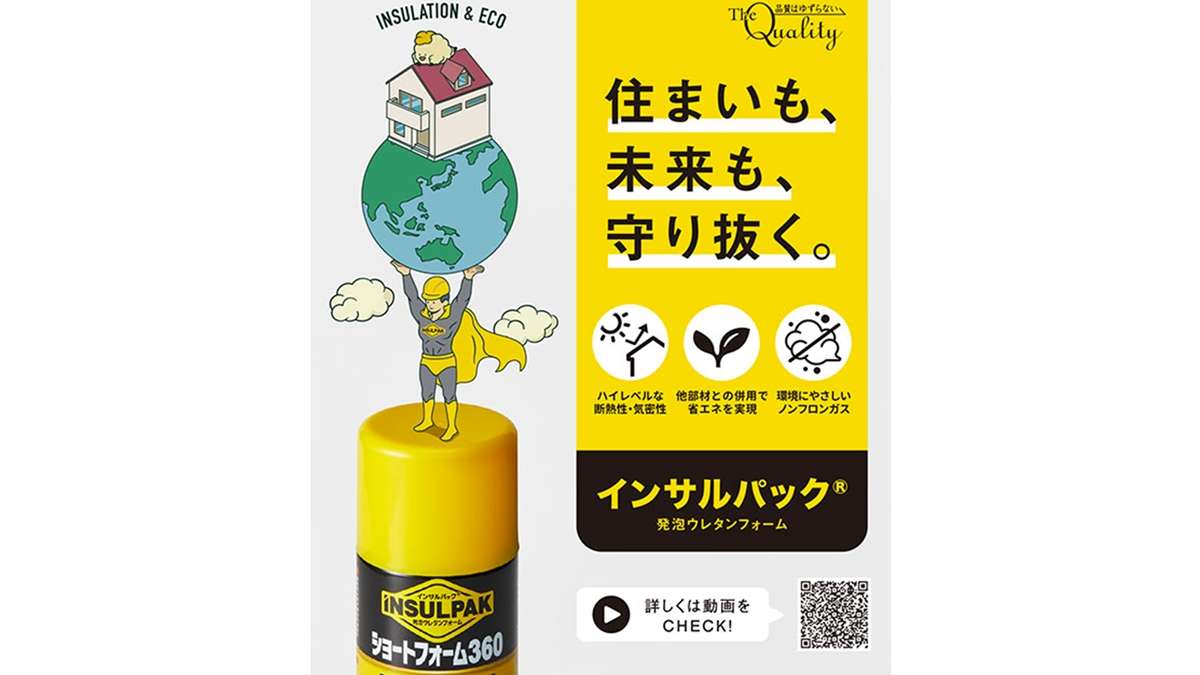

















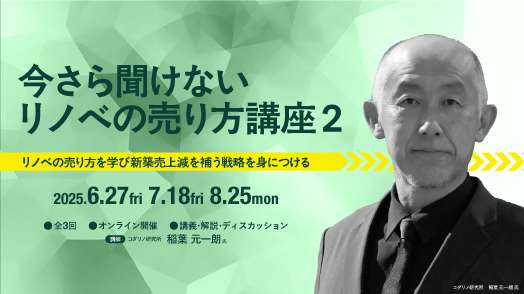
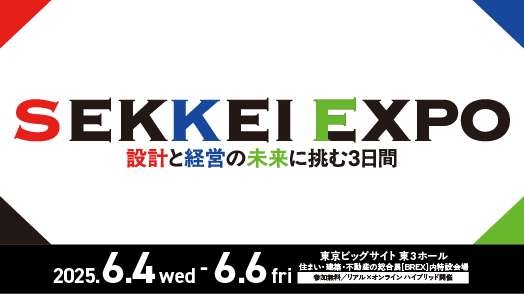



![[改訂版]コンクリート構造物の電気防食Q&A](https://www.s-housing.jp/wp-content/uploads/2023/09/db442e89b62f5b22d830d9615e68f2aa.png)