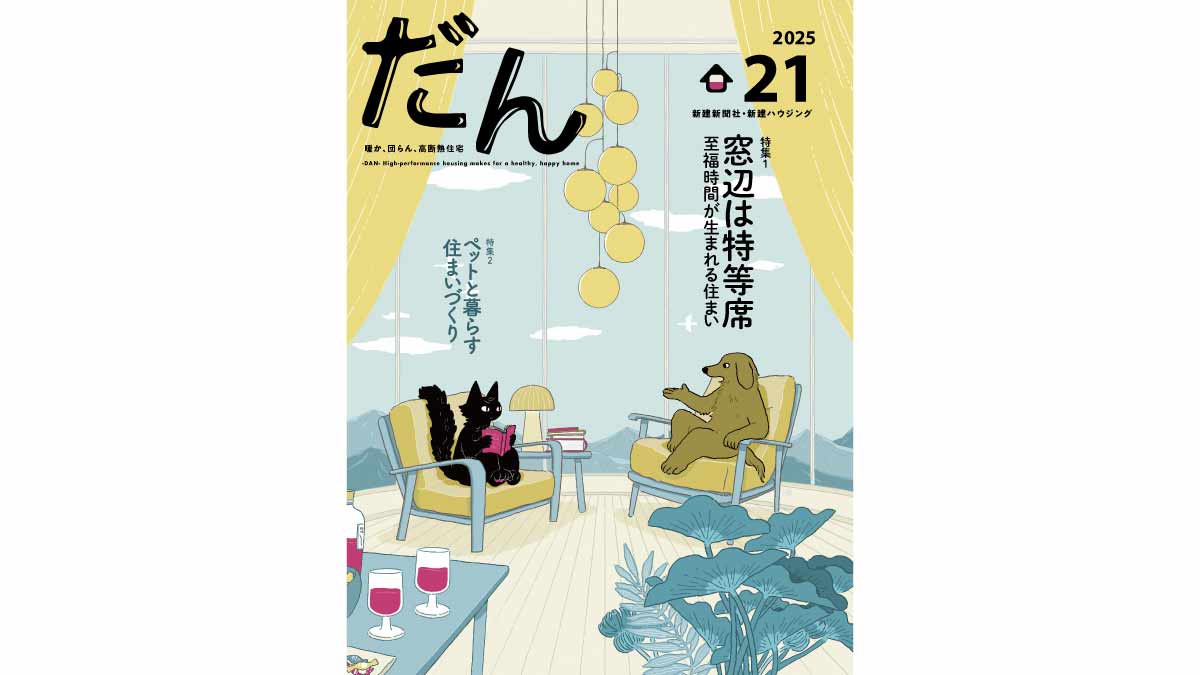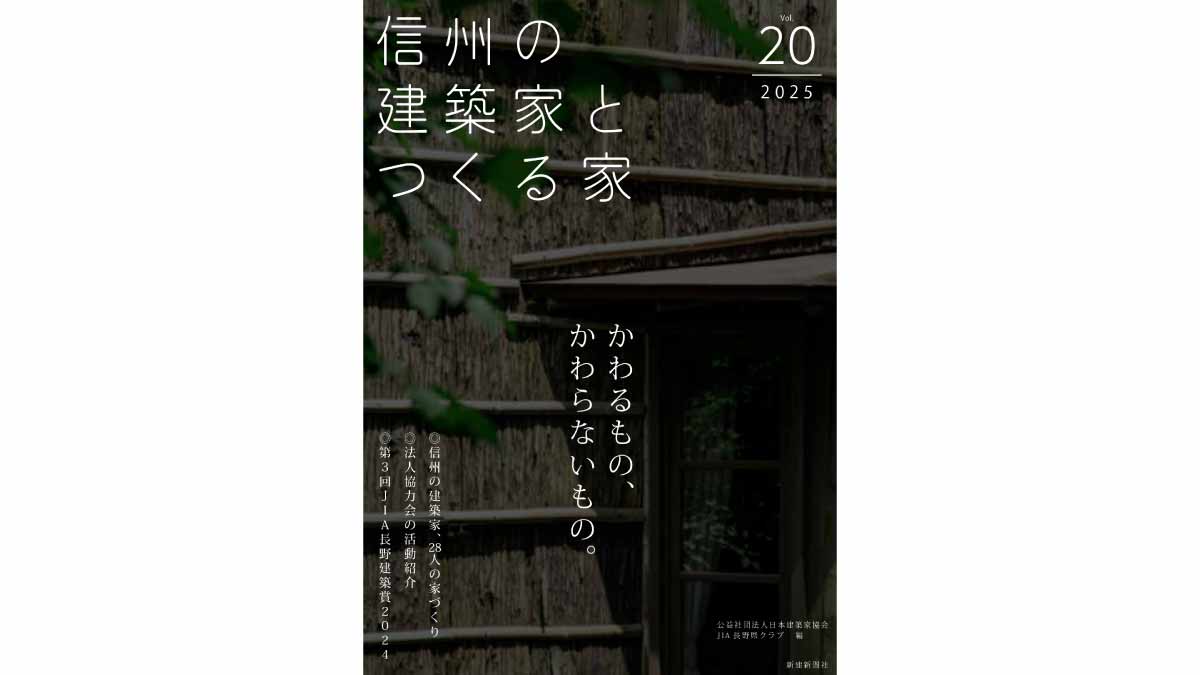屋根や外壁の意匠は、建物の外観を大きく左右する。それだけにどうしてもデザイン優先になりがちだ。しかし、引き渡し後に雨漏りが発生してしまっては、せっかくのデザインもその価値を失ってしまう。今回ご紹介するのは、防水の意識の薄い建物でありがちな雨漏り事例だ。久保田さんが指摘する「設計・施工時に注意してほしい点」を読み取ってほしい。

今回取り上げるS邸は築17年の木造平屋だ。新築事業者とSさんの奥様との相性がよくないため、引き渡し以降は付き合いがなくなっていた。そこで、雨漏りが発生したとき、Sさんの知り合いの屋根業者に相談したのだという。
その屋根業者は「換気棟が原因だ」と判断。棟に用いられている釘頭にシリコンを打って、処理が終わっていた。
それから5年が経過し、雨漏りしたことも忘れていた頃のこと。再発なのか、新たな浸水によるものなのかは不明だったものの、雨漏りが発生した。困ったSさんが別の建築会社に勤める知り合いに相談したところ、第一浜名建装の名前が出てきたということで、問い合わせが寄せられた。
換気棟の製品設計が甘いために雨水が浸入する経路に
Sさんから経緯をヒアリングしたのち、まずは屋根にのぼり、状況を確認。視認した限りでは、換気棟だけでなく、横葺き屋根の接合部も気になった。
ここで、散水調査による検証を行うか、目視で詳細状況を確認する解体調査を行うか、2つの方法を検討した。
ポイントになったのは、「断熱材にセルロースファイバーを採用している」というSさんの言葉だ。散水試験を実施して、充てんされている断熱材を濡らしてしまうと交換が必要になり、Sさんの費用負担が大きくなる。そこで、解体調査を選択することになった。
屋根を外側から目視しただけでも、釘の位置や雨がかりについて非常に危うく感じていた。実際に、屋根の換気棟包みを外してみると・・・
この続きは『新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー3月号(2025年2月28日発行)脱まったり工務店』(P.64〜)でご覧ください。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。


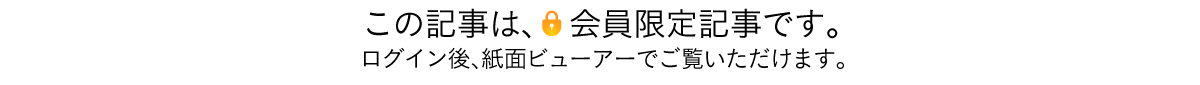


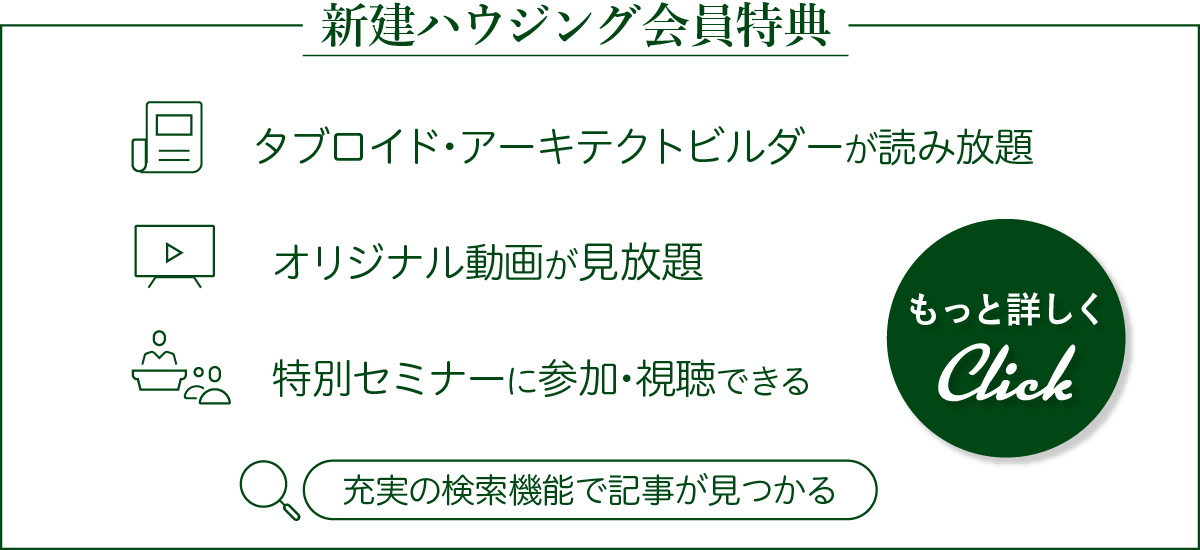



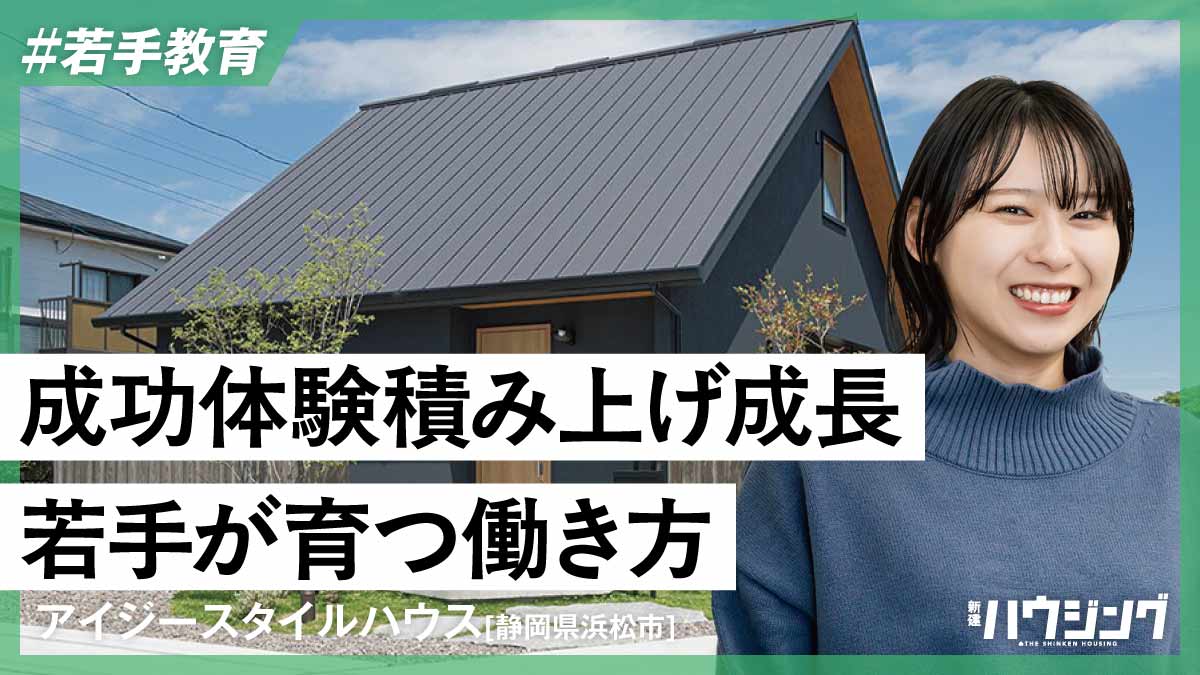
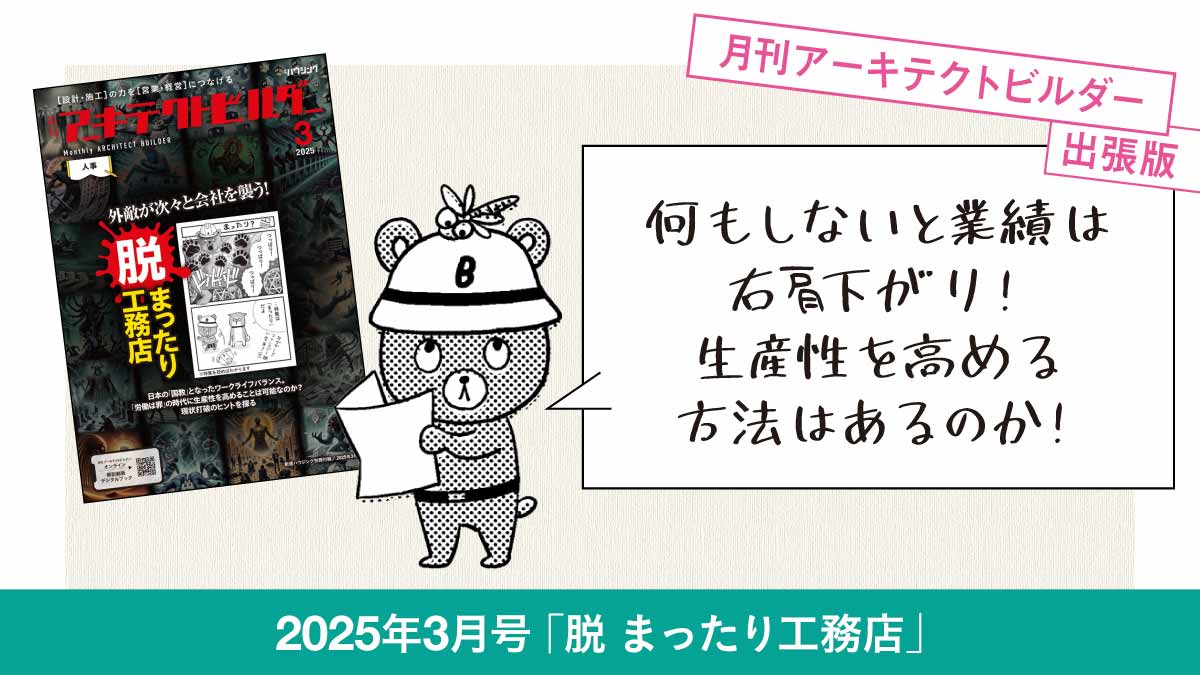









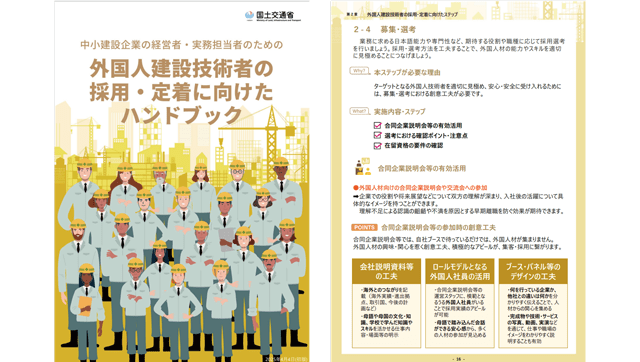









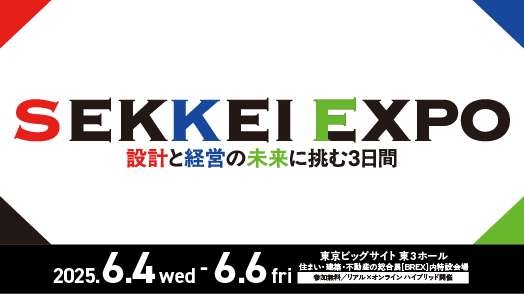

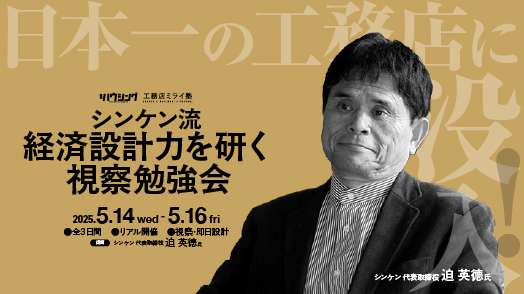


![[改訂版]コンクリート構造物の電気防食Q&A](https://www.s-housing.jp/wp-content/uploads/2023/09/db442e89b62f5b22d830d9615e68f2aa.png)