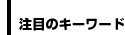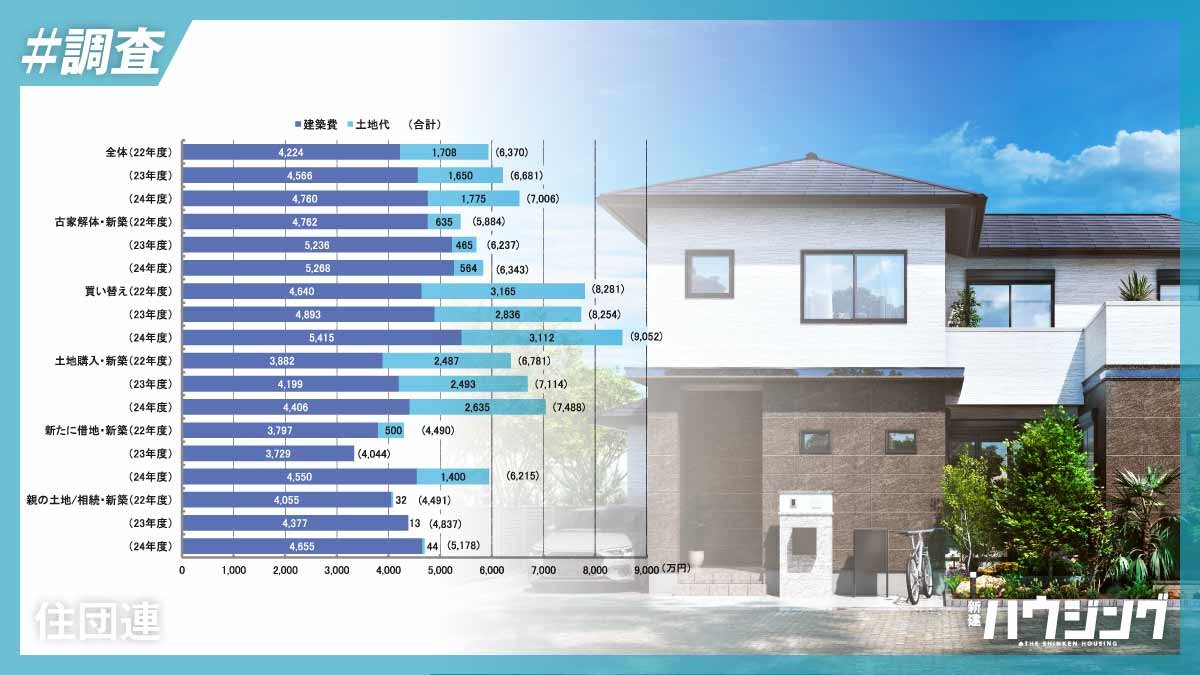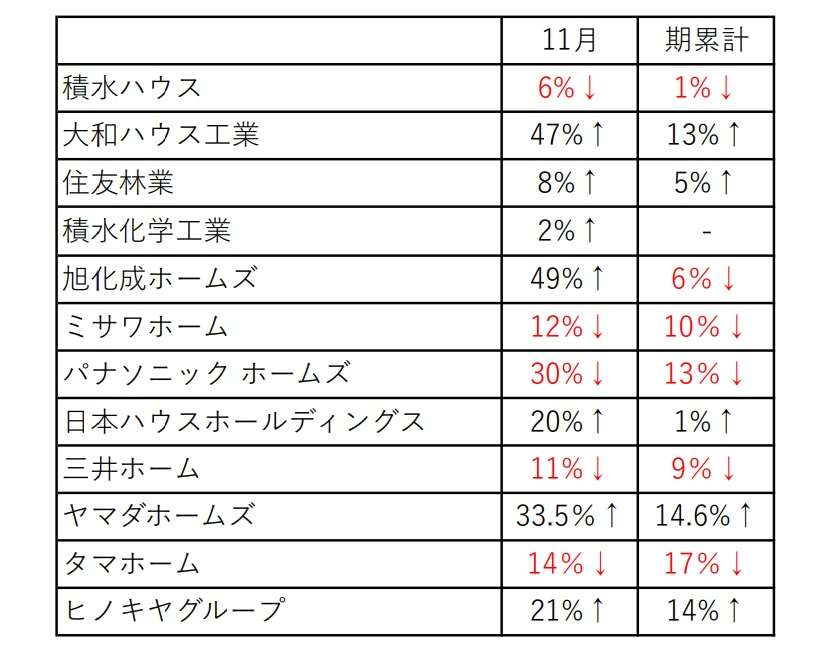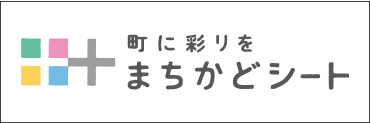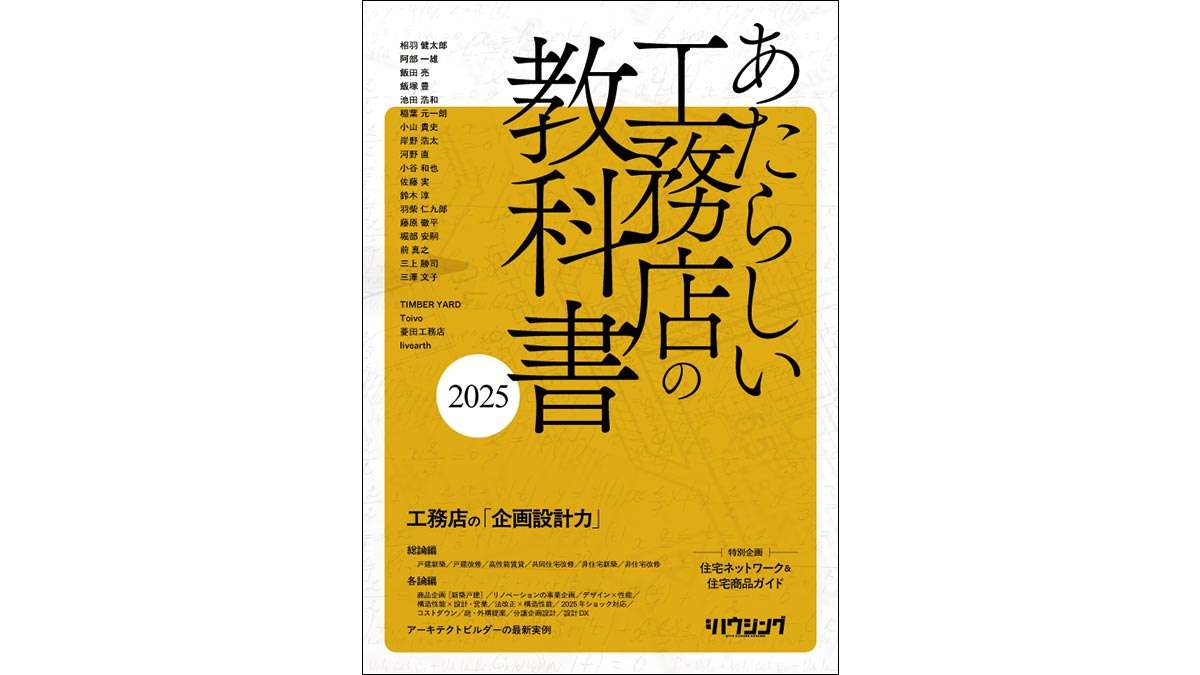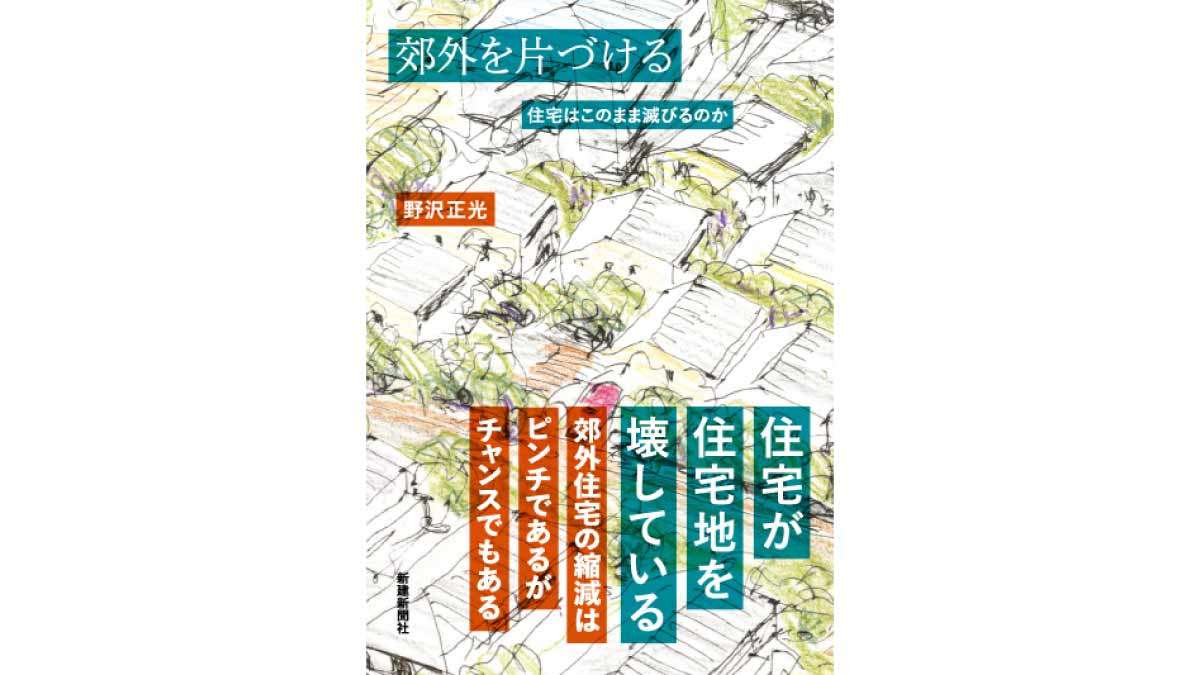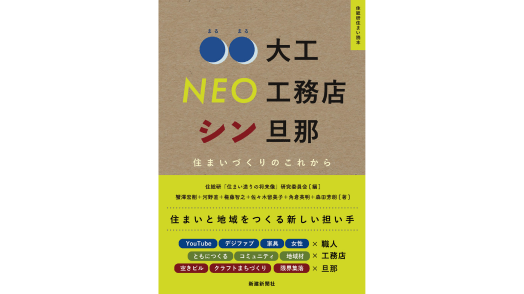さてこの連載企画を読んだ方から「北海道の住宅の歴史」について知りたい、というリクエストをいただいた。わたしは自身を住宅ジャーナリストと自己規定している。研究者的立場ではなく、あくまでもユーザー的目線を心がけているので、そういう意味ではわかりやすい視点を提供できるかも知れない。
たしかに「高断熱・高気密住宅のNEXT(次へ)」という大テーマからは、密接に関わる領域だと思える。
北海道の「住宅史」というテーマではいろいろなアプローチがあるだろうが、わたしは北海道科学大学の故・遠藤明久先生(1915-1995)の「北海道住宅史話・上下巻」を折に触れて参照させていただいている。この稿でも下敷きとさせていただき、個別のテーマで掘り下げてみたい。
国家が「住宅をどう作るか」に直接関与
今回は北海道で、とくに早くから進展した「床の間」の家屋からの消滅というテーマ。
すでに連載第3回で、明治維新と同時進行した北海道の開拓が対ロシアの「国防的」最大テーマであって、明治政府の最大藩閥・薩摩藩の黒田清隆が、先頭に立って日本建築にはまったく発想がなかった寒冷地住宅仕様というものを「洋造」という大方針で、積極的にリードしてきたことをお伝えした。
この性急な「官主導型」の住宅政策、移民拡大への取り組みは、具体的には明治天皇の行幸で中央省庁「北海道開拓使」の実績をご覧に入れた明治14年の北海道行幸をもって「開拓使十ヵ年計画」が終了した。
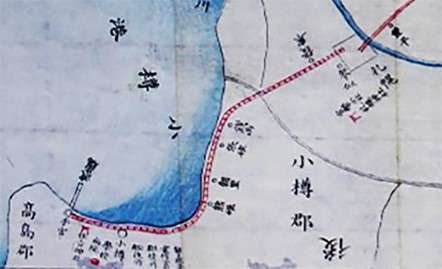
明治天皇行幸の北海道小樽「手宮」港上陸から札幌までの鉄道行程図(出典:北海道大学付属図書館北方資料室)

明治天皇山鼻屯田通輦図〜天皇の開拓状況視察風景(出典:北海道大学付属図書館北方資料室)

明治天皇の休憩施設:清華亭外観

明治天皇の休憩施設:清華亭の和室部分。隣室には本格的な洋間の応接間
国家にとってもこの北海道開拓・民間住宅への関与は未曾有の行政体験だったといえるだろう。民の住宅について国家がそのあるべきカタチを示すなどということは、この10数年間に特異に存在したと言える。
しかし、この民族意思という国家的使命感は、その後の北海道の自治体にまるでDNAのように残存し続けて、今日に至っても北海道住宅局建築指導課という行政主導型の地域住宅啓蒙運動が継続している。こういった官の使命感がいまだに色濃くあるのが、北海道住宅の特異性とも言える。
官の直接的関与は明治14年を境にして急速に減衰し、その後は基本的には民に任せるスタイルに移行した。しかし一度着火した寒冷地住宅としての進化は、徐々に本州地域との乖離をもたらしていくことになる。
「床の間」的ミエ文化から、ホンネの居住快適性へ
わたしたちが「立派な家」という言葉を使うとき、アタマのなかでどんなイメージを働かせているだろうか?そこでは、「高級住宅」であるとか、「大きい家」というようなイメージもあるだろうが、一般的には立派な家というコトバに無意識に「家格の優れた家」という要素がある。
そういったややもすれば「封建的価値感」からはずいぶんと時代が隔たってきているとはいえ、「立派な床柱、結構な床の間」をしつらえた家が想像に浮かんでくるに違いない。

作家・林芙美子自邸(東京新宿区)~作家自身がこだわりぬいた「立派な家」の床の間
上の写真はこだわりぬいた和風住宅として知られた作家・林芙美子の自邸の様子。実際に参観してみて、どういったポイントで「りっぱさ」をイメージしていたかが伝わってきて興味深かった。
作家としてのオリジナリティというよりも、いかにも「伝統的価値感」の方にウエイトを置いている様子がわかる。ここでの価値選択とは、日本的精神性空間として、花鳥風月的に「見る」という価値感が最優先と思える。いわゆる「居住体感性」というものはひたすら自然に「ゆだねて」いる。庭と一体化した温湿度感が体感の内容なのだろう。
外界との結界は障子紙1枚のみ。その上、障子は上下させることで通風を最優先している。まことに「開放的」。年平均気温が18度前後で冬期間でもめったにマイナス気温にはならない温暖な本州・首都圏地域で冬の寒さは「我慢」することで成立するのだろう。
総坪数300坪という敷地は、流行作家としても荷の重い出費だったとされているが、この「庭との一体感」が不易な家の価値と考えたのだろう。築後80年ほどとされるが、この「いごこちの外界依存性」は各地域で気象条件の違う列島社会では、「風流」の押しつけかもしれない。
一方でこちらは東京の林芙美子邸に30年ほど先だつ110年ほど前、札幌市北区に建てられた作家・有島武郎の家の1階にしつらえられた床の間と、その窓側空間。先に見た清華亭建築からはさらに30数年後、札幌市の北大近くに建てられた(写真下)。


当時、有島武郎は北大の前身の大学で英語講師をしていたが、賃貸住宅を転々とするくらしの末に自ら設計に深く関与して新築した家。それまで借りていた賃貸住宅では、上の林芙美子邸と同様に「りっぱな」床の間付きの家が、当たり前の日本人的「家の価値感」として本州以南地区とほぼ同様の仕様で建てられていた。
それに対して、有島は欧米人の建築士事務所スタッフと話し合いながら、この新築計画に向かっていたとされる。結果として、床の間はごくさりげない仕様とし、その窓辺側は洋館の「上下窓」仕様で、しかも床までとはせずに、あえて下部は和風の収納を配置している。
しかもご丁寧に床の間の横には洋風窓を見せているし、また、この和室の入口は洋風ドアであり、家の真ん中の「ホール」から出入りする設計。開けてすぐ見える正面には洋風の硝子窓が目に飛び込んでくるようにデザインされている。建築としては、床の間付き和室の「お約束」の縁側が存在せず、そこで外界の寒冷な自然とは重厚な仕切りを造作している。
一応は日本人的な生活文化習慣に配慮しつつ、しかし温熱環境的には明確に外界と遮断するデザインとしている。この「和室」は玄関から入ってすぐの居室で来客応接を考えたものと言える。寒冷地北海道に住んでいるとはいえ、日本文化への同調姿勢は感じられる。
しかし外観デザインは完全に「洋館」風であり、開拓期からの北海道住宅がたどってきた軌跡を十分に感じさせてくれる。ちなみに外観デザインはこちら(写真下)。

作家・有島武郎邸~作家自身が設計した洋館スタイル。現在は札幌市の管理で「芸術の森」に移築展示されている
この有島邸は北海道の住宅デザインとして次第に本州地域の伝統的スタイルから大きく離陸していく号砲のような外観だったことだろう。
当時の地元新聞メディアでも「こんな変わった家がある」と紹介されていたという。マンサード(中折れ屋根)が特徴的なフォルムといい、雪景色の中でも「映え」があったと思えるカラーリングもそれまでの日本住宅の伝統的なありようからは大きく乖離して、度肝を抜いていたことだろう。外観の右手前側が、床の間のある応接和室に相当している。
本州地域のように伝統的価値感が継続し続けた地域と相違して、性能を追求していく中から、徐々にデザインでもまったく違う潮流が、主導していくことになる。
この有島邸が嚆矢(こうし)となって、札幌市内で大学教授・知識人の家というのがひとつの住宅デザインの最前線のようになっていった。そういう「住文化」が花開いていくことになるのだ。
《次回に続く》
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。