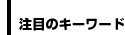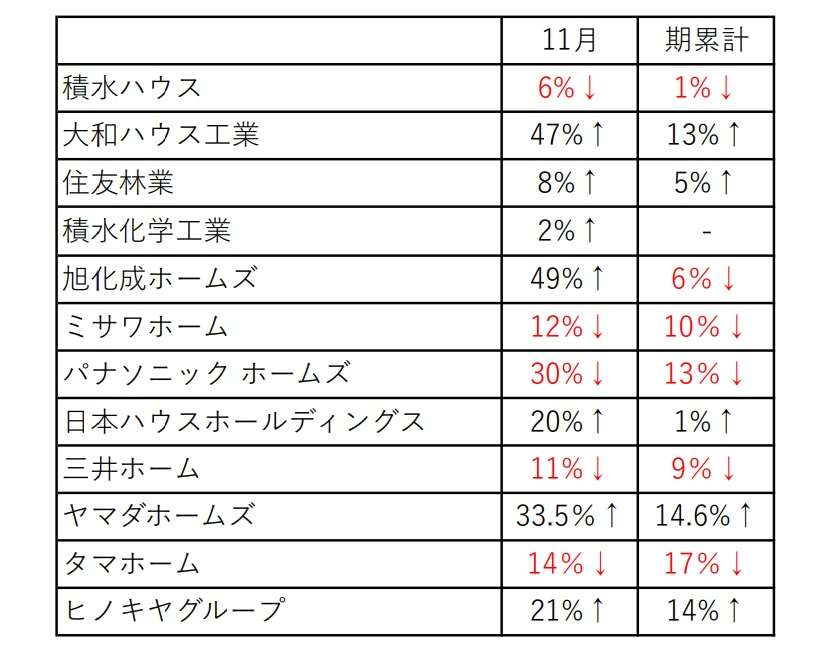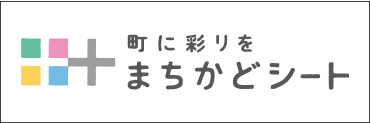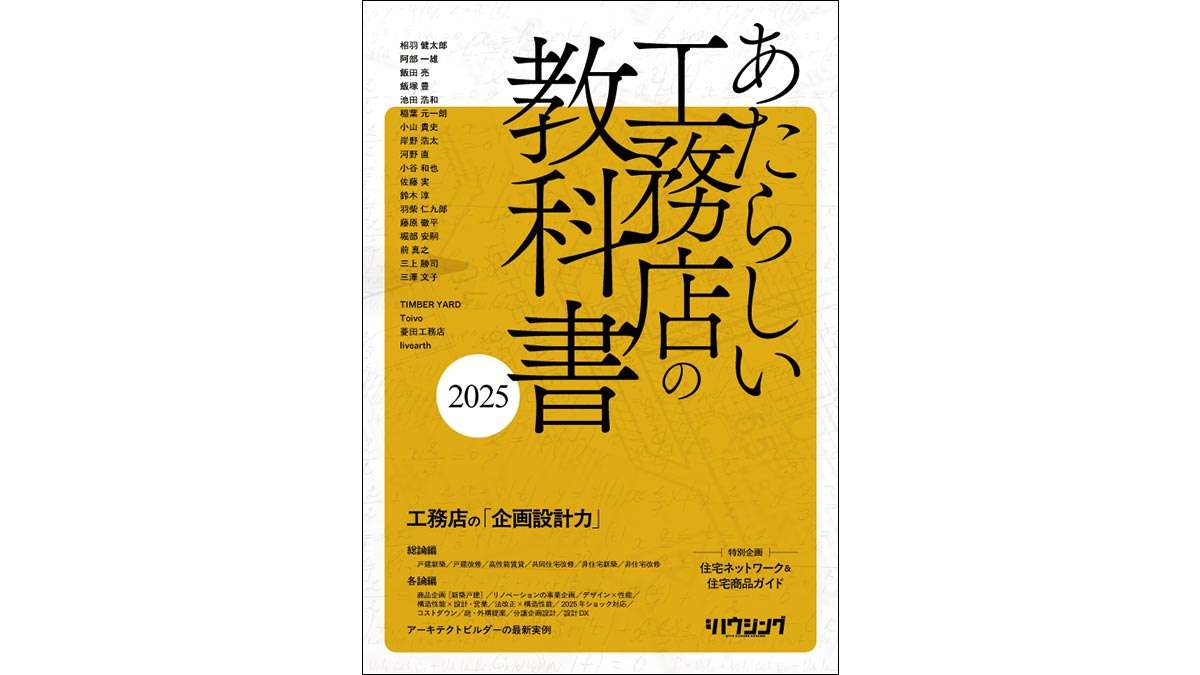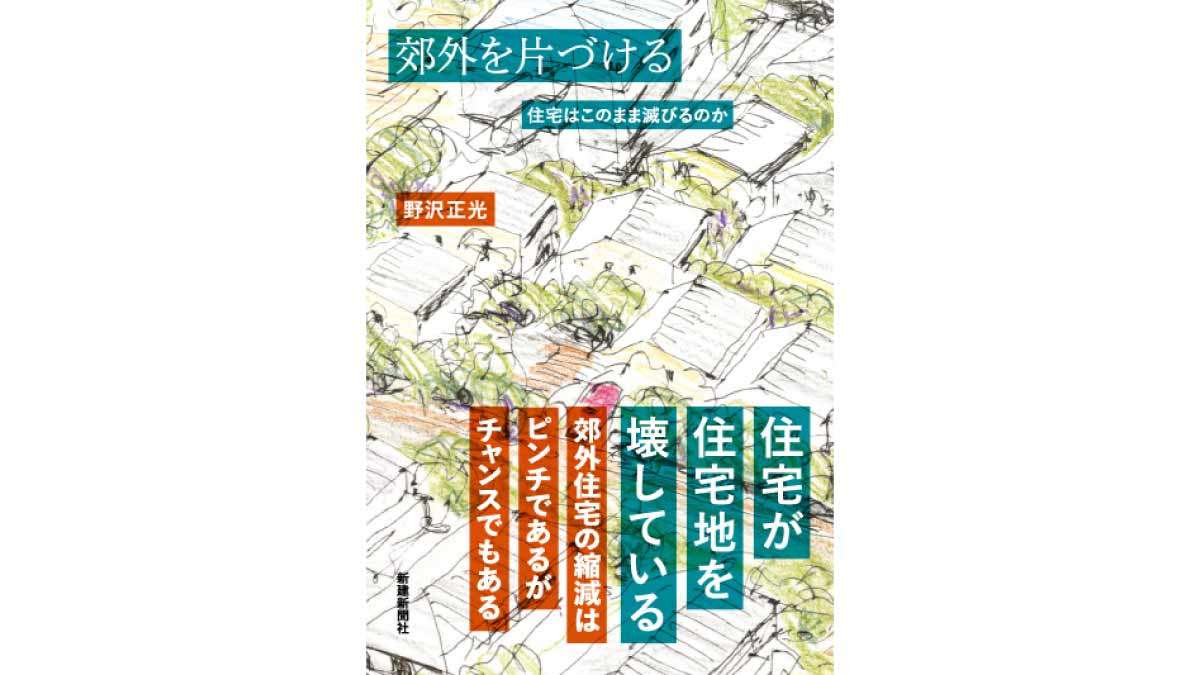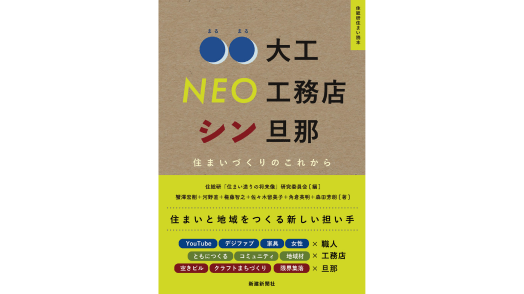僕たちだからこそできる
野沢:僕は「 一般社団法人住宅遺産トラスト」という団体の代表理事もやっています。どんなに優れた住宅でも、個人の所有である住宅の継承は難しいテーマです。優れた住宅を失うことは、それがなくなるだけに留まらず、地域の記憶、地域の景観を失うことになる。こういった重要な住宅資産を「住宅遺産」と呼んで、関心を寄せてもらいながら、後世に残す取り組みをしています。
優れた建築や景観、まちなみを残していく社会的な仕組みが、昔も今も確たるものとしては存在しないということです。それは社会が要求していなかったのか、それとも建築という業界が考えていなかったのか・・・。これはとても大切なテーマだと思うんです。建築だけに限らず、どんな分野においても共通すると思うんだけど、いい物を自分の目で見て、それを血肉化することで、初めて吸収でき、自らのつくるものに反映できる。知識としてただ知っているじゃだめだと思う。
だから、という訳ではないが、工務店もたくさんの引き出しを持っておくことは大切だと思う。目の前の仕事を充実させるには、自分なりの“余白”の部分というか、蓄積したたくさんの知識を引き出しながら、設計したりつくったりしてみたらどうだろうか。もちろん経営も、標準化も合理化も大切だけど、それとは別の視点を持つこと。「みんながこうやっているから」ではなくて、「いや待てよ?」っていう問いができるかどうかだと思う。そういうことを考えたり創りだしたりするのが大切。それもひとりでやるんじゃなくて、「府中」では迎川さんたち地域工務店と一緒になって楽しみながら取り組んだ。それが地域に一定の提案ができた理由だし、結果、貢献できた理由だと思う。
既存の常識を疑うというか、一旦立ち止まってみることが大切なんです。例えば、新型コロナウイルスの感染が拡大してから、アメリカやヨーロッパの飲食店は、密を避けるために、道路の一部を使って勝手に路上カフェを始めた。これって大げさなことではなくて、私たちもこういう“大胆さ”や“したたかさ”みたいなものは、自分たちの責任で、自分たちのやれる範囲で実行するのも必要だと思う。法律のしばりなど、何かをさせない規制を一旦忘れてね。
僕は、木造ドミノ研究会の皆さんと共にささやかでもいいから地域に根差したまちづくりをあちこちで考えていきたい。そのためには、今ある社会について、あるいは自分たちの専門領域について、すこし冷静に俯瞰してみたい。否定するために眺めるのではなくて、ポジティブに批評するということ。僕たちには、僕たちだからこそ、やれることがあるはず。
求められる“不動産型工務店”の意味
野沢:実は建築家がつくる住宅も、長いスパンでみると難しいところがあるのではないかと思っている。建築家の宮脇檀(みやわき・まゆみ)さんが手掛けた極めて優良に計画された住宅地も高齢化が進んでいる。立地も丘陵地にあるところもあり、一種の閉じたゲートコミュニティーになってしまっているように見える。関係のない方は入らないでください、と。こうした住宅地も様々な事情を抱えているのではないか。これからはそうした住宅地についてもそれをケアしたり、長期的なスパンで考えていくような修復型のコミュニティー形成を考えることも必要だと考えている。
こうした地域のサポートは工務店を核としたグループがこれをやらないで、誰が担っていくのか。
ハウスメーカーやデベロッパーが手掛けた無味乾燥なまちなみ、フェンスで仕切られた住宅が立ち並ぶ凡景。それがこのまま、ケアなしで豊かな暮らしを育てるまちになるとは私には思えない。こうしたまちを修復する、理念や思想みたいなものが大切なはず。木造ドミノ研究会は、そういった面も期待をされていると思いたい。
迎川:僕たちが子どものころは、家と家の間にフェンスなんてなかったよね。近所のお友達と家と家のあいだを走り回ったり、かくれんぼや缶蹴りをしたりした。それを許容する文化だった。いまの住宅地でそんなことできっこないよね。
野沢:まさにその通り。ある著名な作家の本で、「善意」と「悪意」に関することが触れた一文がある。私なりの解釈をすると、善意のまちは、建ぺい率が6割でも、6割は決して建てない。3割5分くらいの家が建っていて、それで十分でしょうと。悪意っていうのは、埋めるだけ埋めて使い切ってやろうと6割隙間なく家が建つ。家と家の間が詰まりきっている。
住宅寿命が極めて短い。これは業界の人たちもよく理解しているんじゃないのかな。これを続けていると、今日稼ぐためには何とかなるかもしれないけど、いずれジリ貧になるだろうと僕は思う。
三浦:その意味では、今の話でいくつか受け取った話があります。ものすごくシンプルに言うと、工務店が不動産と建築を一緒にやる「不動産型工務店」みたいなあり方が求められているというのが1点。2点目は「越境していく」ということですよね。今まで建築だけやっていた工務店から、不動産も、そしてコトづくりからコミュニティーデザインに至るまでやっていった方がシンプルに言うと、いいまちづくりができる。そしてやりがいもあって、お客さんや社会のためにもなる。
問題は何でそうなったかというと、あえて挑戦的に言うと野沢さんたち世代が悪い(笑)。
一同:(笑)。
三浦:極論を言うと、土地を金儲けの道具に使って、どんどん希少価値を上げた結果、不動産屋がそこに群がって、土地が値上がりし、いつの間にか利権を主張するようになった。その流れの中で、コミュニケーションもなくなり、窓を閉め切って、フェンスとフェンスで区切られた家と、まちなみができてしまった。
野沢:まったくその通りだと思う。
三浦:そこを抜け出すためには、「土地で儲ける」という発想から抜け出さない限りは、この話はどうにもならない。ただ工務店が土地を持とうと思っても、値段がネックですよね。土地は高いし、そもそも土地を扱うこと自体にリスクがありすぎる。土地の値段が限りなくゼロに近いアメリカみたいになれば、今の話は別ですが。
野沢:僕はものをつくる人間として、その時代を生きてきた。たとえば日本住宅公団という組織がありましたよね。当時公団は、完成した時の価格についてはほとんど考えていない。つまり売らない前提。建てた住宅は売却しない前提で、賃貸で回していくことを考えていた。当初は住宅をストックとして考えていたんです。途中から政治家が出てきて、カネを生むために分譲住宅の供給に転じざるを得なくなる。高度成長期にはとにかく経済を回すことを優先に、経済を優先させるんだっていう雰囲気があった。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。