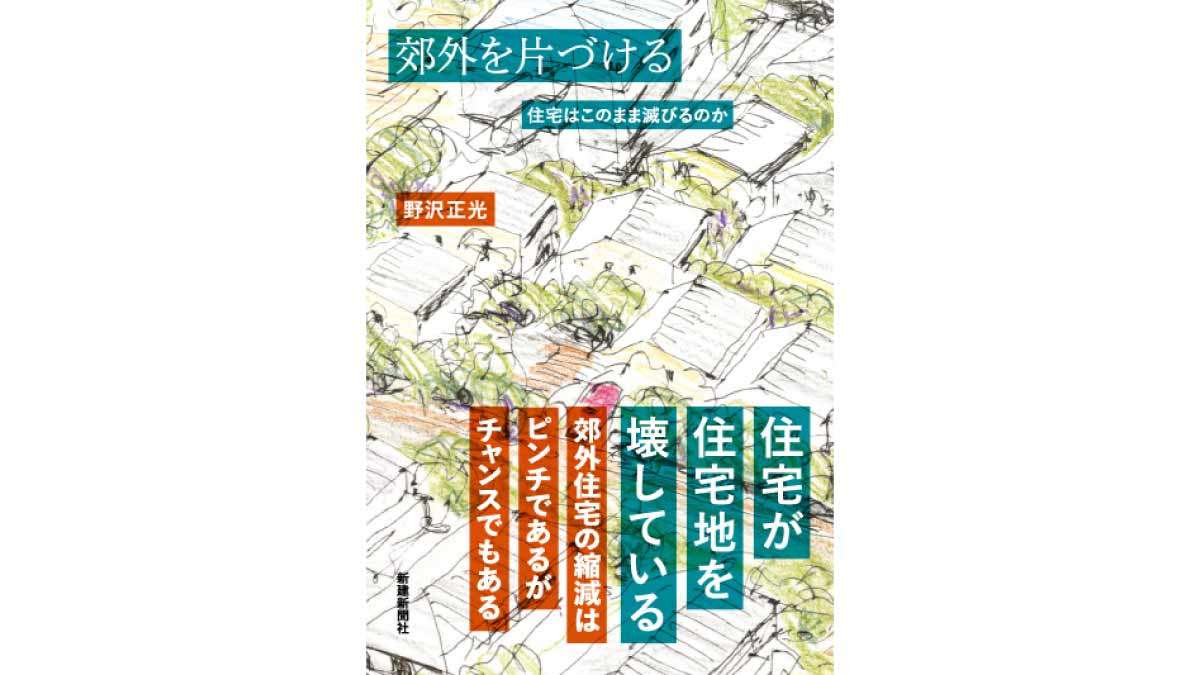新潟中越地震から1カ月経った11月26日、本紙記者は激震地・川口町に三たび入った。被災した人びとの生活、その暮らしの建て直しに向けた願い、そしてその不安はどうしたら解消されるのか−現地で直に聞きたいと思ったからだ。今回は被災したおふたりの話を中心に現地をレポートしたい。そこではおふたりとも「荷物を運び出せるだけでもまだいいほう」といい、家屋の修理や建て替えにはとても手をかけられない生活ぶりだった。不安や悩みばかりが増幅する。被災者の大半がそうした生活を余儀なくされていた。
■100mの範囲で建物被害に明暗 いまだ荷物を運び出せない家も
本震から約1カ月経った川口町。国道17号線を走り片側通行で渋滞するトンネルを抜けると、屋根や壁にブルーシートをかけた家が一気に目立った。
同町に住むKさん(32)は、地元のお寺・D寺の住職で母親とふたり暮らし。2階を本堂、1階を生活の場とするそのお寺は、国道沿いの山際に建つ。斜面を切り崩して昭和8年に建築した木造建物。応急危険度判定の赤い紙には、背後の地山に崩壊のおそれがあると記されている。
「突然ドーンと(地震が)始まった。電気がいっぺんいパツッと切れて、何がなんだかわからない。爆弾を落とされているんじゃないかと思いました」とKさん。
谷側の土留め擁壁はすべて倒れ、増築を繰り返したRCの壁は打ち継ぎ目で分離した。内部も壁が崩れ天井がたわみ、住める状態にはない。
「余震のたびにゆがむ。補強するところはしたいが、2階の本堂へは危なくてもう人を上げられない。でも家があって、荷物を運び出せるだけでもいいと思わないと」。Kさんはそう話す。
12月には自衛隊のテント生活から仮設住宅へ。「家の場所、生活のしかた、被害の度合いなど、被災者の事情はそれぞれ違う。一律に問題が解決できるものではありません。しかし何とか暮らしを立て直したいとみな願っている」とも。
「ここは1歩山に入るだけで、雪の深さが違う。家から離れて暮らすのは、はかりしれない不安があるでしょう。川沿いの平地で家が倒壊せずに残った人であっても、亀裂の入った基礎をきちんと応急措置してもらえるか、修繕してもらえるか、そんな不安で気が休まらない。先の生活へ、個々の心配は尽きません」。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。








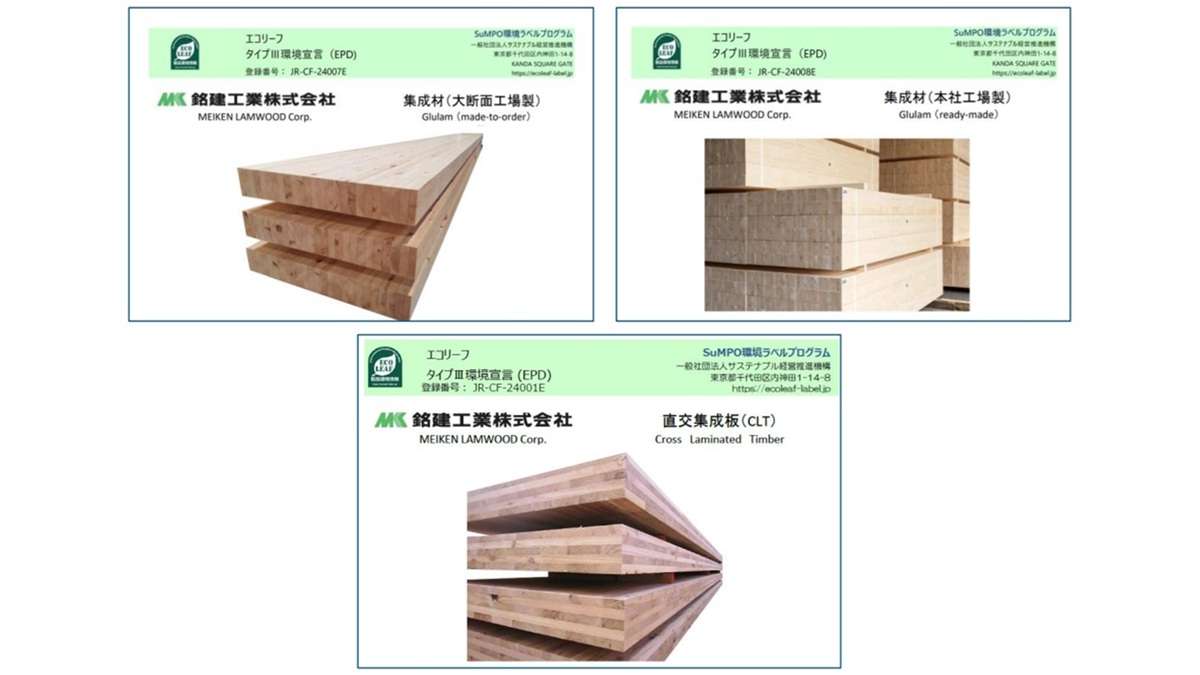




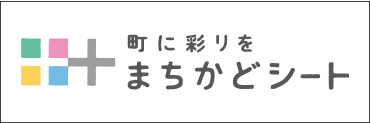










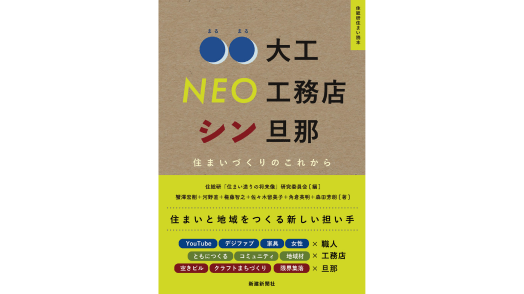
![[改訂版]コンクリート構造物の電気防食Q&A](https://www.s-housing.jp/wp-content/uploads/2023/09/db442e89b62f5b22d830d9615e68f2aa.png)