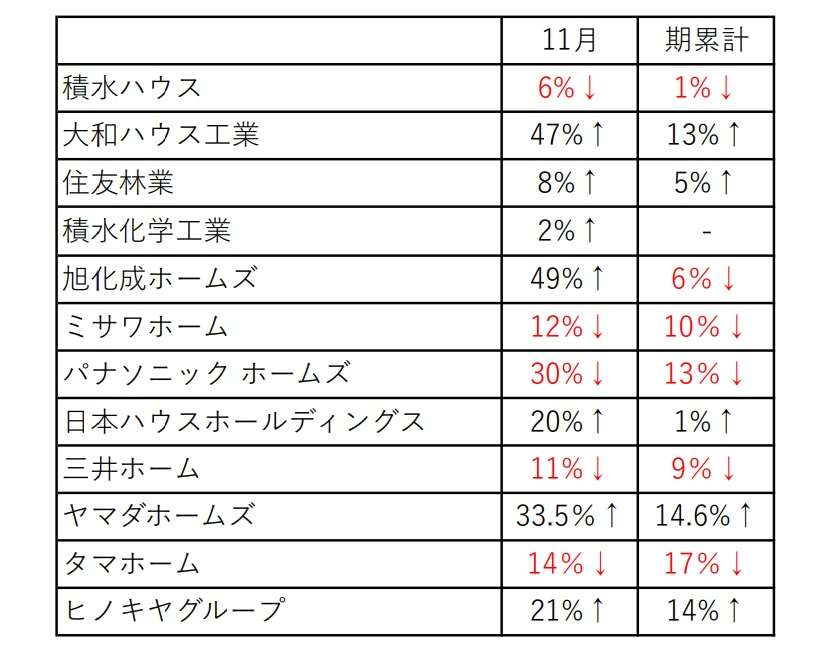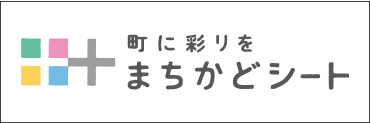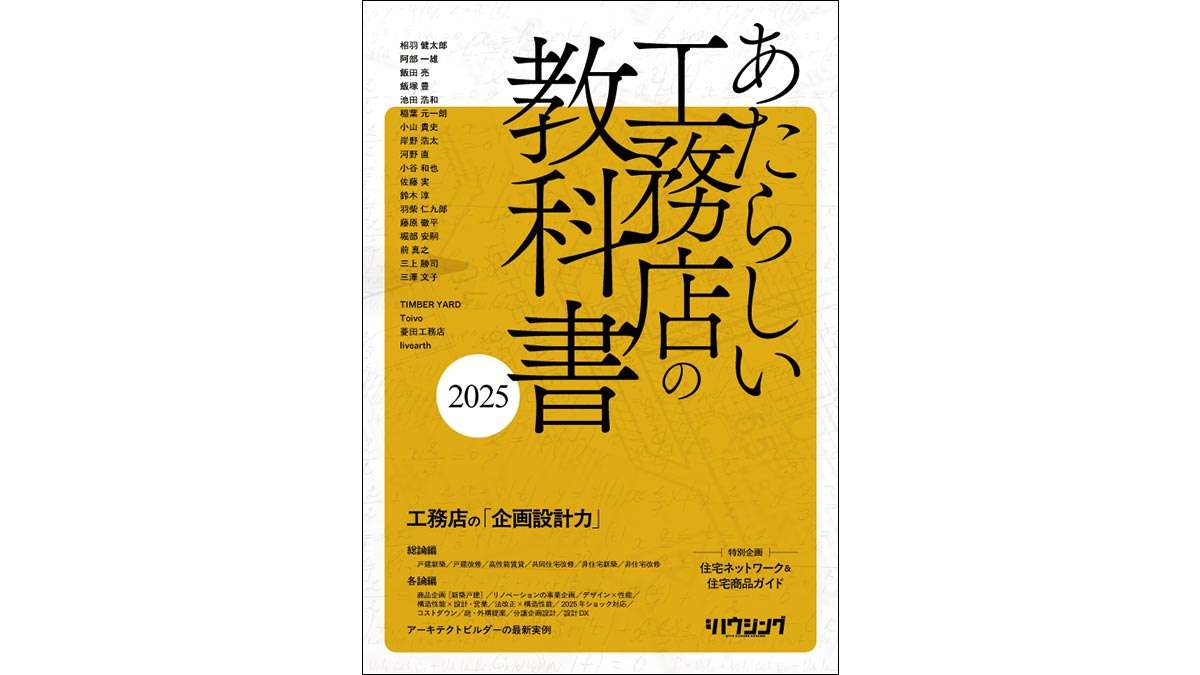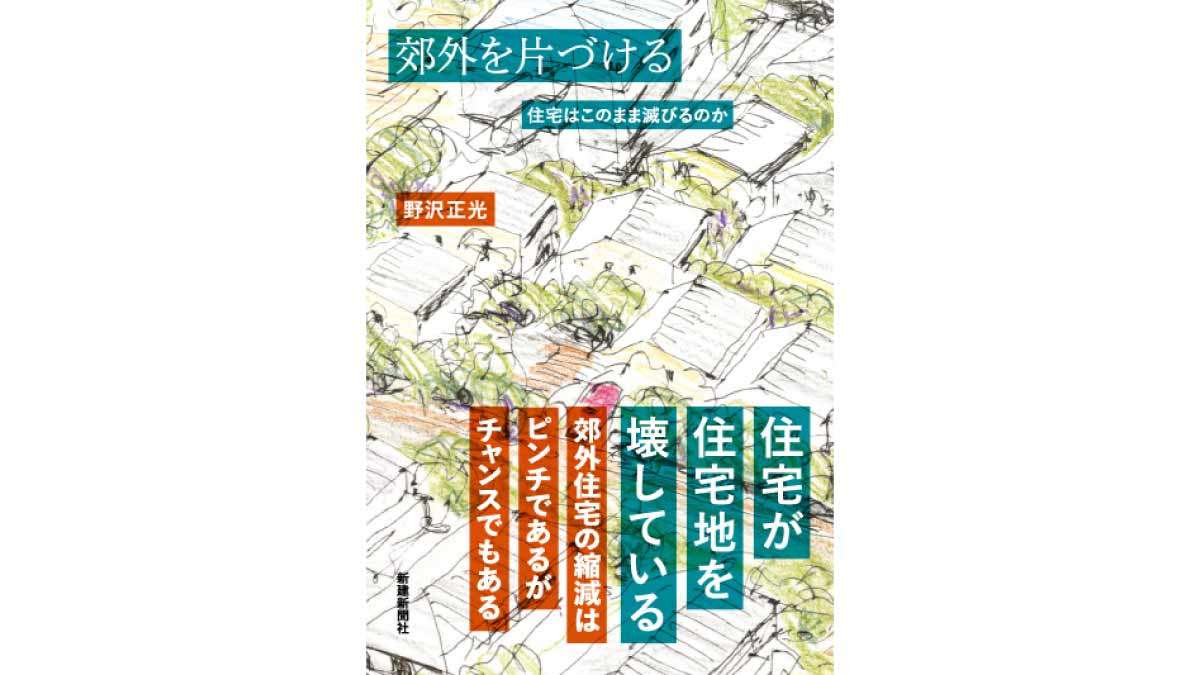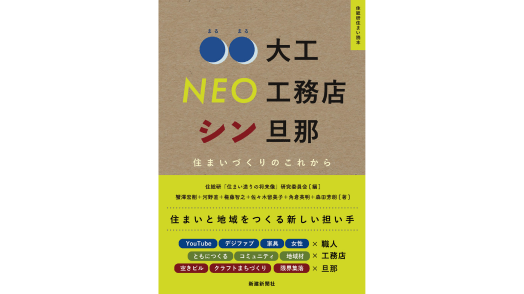新建ハウジングプラスワンに連載いただいている加藤大志朗さんの「家と人の内面を歩く」。ここでは5月号に掲載した「言葉。」の全編を掲載します。写真も加藤さんによるものです(編集部)。

大人の魂を射る子どもの眼差し
手元にある詩集を開く。
1959年(昭和34)、岩手県岩泉町の小学3年生・K子ちゃんによって書かれた詩である。
働いた手 ぶかっこうな手
ちょっと見れば
男と まちがえられる手
たわしがけした手
ひびをきらした手
いっしょう なおらない手
薬がほしい
骨までなおる 薬がほしい
昭和30年代の岩手県、とりわけ北上山系は「日本のチベット」と称され、電気、水道、ガスもなく、ほぼ自給自足に近い貧しい生活を強いられた地域である。小中学生の多くは家の手伝いや山仕事、家計の手助けのために奉公に出され、日々の勉強も疎かとなった。
昭和40年代に入っても無介助分娩は半数を超え、さらに奥地の寒村では乳児死亡率が1000人あたり200人を超えている(平成19年度の全国平均は2.2人)。
過酷な暮らしに多産多死の現実が重なるなか、子どもたちは学ぶことへの憧憬を抱きながら、学校で学んだばかりの言葉を駆使して、感情を綴ったのである。
この詩は小3の女の子が山仕事によって、いつの間にかその手が男の人のように無骨なものとなり、その薬がほしいという叫びを言葉にしたものだ。「骨までなおる薬がほしい」という最後の言葉に、10歳に満たない少女の切実な夢と願いが凝縮されている。
わたしのうちに
牛が七とうもいたのに
かわいそうに 一とう
しんでしまいました
牛の子をなせないで
おなかをやんで
しんでしまいました
「やさしい牛だったのになあ」
とかんがえながら
わたしはないています
お母さんと しずかに
「ねえ やさしい牛がしん
じまったね」
といって
二人でないています。
(M小2 R子)
難産の末に死んでしまった牛を、R子ちゃんは「やさしい牛」と表現している。7頭の牛の1頭1頭の性格を、この少女は見抜いていたに違いない。
心打たれるのは、哀しみに暮れて泣いているR子ちゃんに、母親が寄り添う姿が表現される「二人でないています」の1行。母親はそばにいるだけではない。「やさしい牛がしんじまったね」という少女の、その気持ちに寄り添っているのである。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。